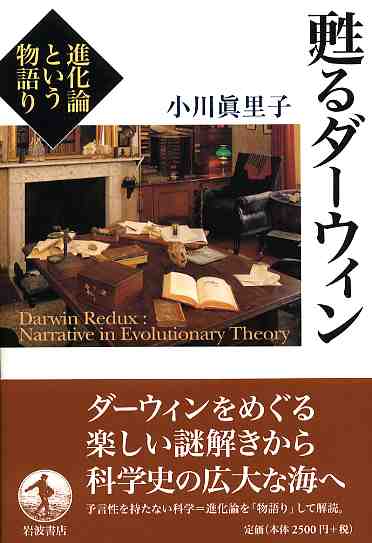 【書名】甦るダーウィン:進化論という物語り
【書名】甦るダーウィン:進化論という物語り【著者】小川眞里子
【刊行】2003年11月14日
【出版】岩波書店,東京
【頁数】xiv+253+3 pp.
【定価】2,500円(本体価格)
【ISBN】4-00-002396-9
【備考】『図書新聞』(2004年1月31日発行・2663号)掲載の書評原稿
【書評】※Copyright 2003 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
歴史上のひとりの人間で,公私にわたってダーウィンほど徹底的に調べ上げられた人物はほとんどいないだろう.一次資料の整理と公開を長年にわたって積み重ねてきた結果,近年のダーウィン関連本といえば,電話帳のような伝記とか,何10冊にも達する書簡集とか,とにかく詳細をきわめた網羅的かつ大部な新刊が少なくない.それだけに,ダーウィンに関する新しい本を書くためには,きわめてハードルの高い仕事が要求されるようになっている.ダーウィンに関する新しい事実を発見するとともに,ダーウィンを読み解くための新しい視点を提示することが,新刊著者には期待されている.
本書は,ダーウィンの著作を〈物語り(narrative)〉という観点からもう一度読み直そうという問題提起をしている.極東にいる科学史研究者にとって,イギリスで生涯を送った人物について調べあげるのは容易なことではなかっただろう.著者は,ダーウィンの書簡や資料などが保管されているケンブリッジ大学に滞在したり,ダーウィンが生まれ育った故郷を訪れたりして,進化学の〈オリジン〉がイギリスのどのような社会・文化・学問的な環境のもとにあったのかを探し求める.
シュローズベリーにあるダーウィンの生家について論じた第2章では,シュローズベリーという土地がイギリス産業革命の時代に果たした大きな役割を指摘し,それと彼めることでダーウィン家の系譜をたどる.続く第3章では,ダーウィンの主著『種の起源』がどのように「ことばによる物語り」読まれてきたのかを,キリスト教の創世記・生物の地理的分布・自然淘汰のメタファーという観点から再検討する.さらに,第4章では,ダーウィンの数ある著作の中でも,人間を含む動物の情緒表現を論じた異色の書『情動の表出』を取り上げ,ダーウィンが当時最新の技術だった写真をどのようにとりこみながら,「図版による物語り」をどのように編み上げていったかを考察する.この章は,表情の分析がいまなお未解決の点が多々ある分野であることを教えてくれる.第5章は著者による新発見物語りである.『種の起源』に登場する牛の育種家“コリンズ”の正しい名前が“コリング”だったという事実を出発点として,著者はダーウィンが自らの自然淘汰理論を構築するにあたって参考にした当時の育種家たちの業績を振り返る.遺伝のメカニズムがわかっていなかった当時のイギリスで,家畜やペットの育種家たちが果たした役割を再認識させられる.最後の第6章は,アウグスト・ヴァイスマンを主人公として,「死の進化」というテーマの論考である.
全体を通していえることだが,読みこむほどに勉強になる本だ.50ページあまりにわたる詳細な「注」は情報量バツグンで,これまで知らなかった文献や資料について教えられることが多かった.また,「付録I:ダーウィン関係の資料について」は,現在入手できるダーウィンの一次資料や関連資料を網羅的に挙げている(インターネット資源の存在をもっと示してもよかったのではないか).これだけ内容の詰まった本なのに,肝心の人名索引・事項索引が付けられていないというのはまったく不備だと思う.まさか「〈物語り〉だから索引はいらない」などというわけではないだろう.
さて,私が反論したいのは第1章,とくに本書全体を貫くとされる〈物語り〉というキーワードである.私の結論からいえば,このキーワードは本書にはまったく不要だっただろうと思う.歴史学で言う〈物語り〉という用語は激しい論争の中心にあった.たとえば,第1章で言及されている歴史〈物語り〉論はそのまま鵜呑みにすることはできない.著者は:
グージの「物語り的説明」は,批判もあるが今日多くの支持を得ていることも確かである.(p.26)
というのみで,歴史〈物語り〉論をめぐる賛否両論についてのフェアな紹介を怠っているように私には感じられる.たとえば,〈物語り〉論の現代における旗手であるヘイドン・ホワイト(たとえば『物語と歴史』を参照)については好意的に紹介しているのに,彼に対する最大の批判者であるカルロ・ギンズブルグ(ヘイドン・ホワイトを正面から批判した『歴史を逆なでに読む』や歴史〈物語り〉論に反論した『歴史・レトリック・論証』などがある)には言及していない.〈物語り〉というキーワードが歴史学で果たしてきた史的背景について,著者はもっと論を尽くすべきではなかったか.
第1章「進化論とはいかなる科学か?」では,進化理論のテスト可能性(ポパー的な意味での)への批判に対抗して「〈物語り〉的説明」を擁護しようというのが著者の基本的スタンスだと理解した.それは大筋でまちがってはいないだろう.しかし,典型科学としてポパーが念頭に置いていた一般化科学(物理学のような)に進化学のような歴史科学を対置させる上で,〈物語り〉を前面に立てるだけでは力不足だと感じる.なぜ〈物語り〉だけでは力不足か――この本では〈個物(individual)〉 vs 〈クラス(class)〉という基本的な対置がまったく論じられていないからだ.〈物語り〉論を言いたいのであれば,まずはじめにその「主体(central subject)」が何であるのかを論じなければならない.物理学のような一般化科学でいう法則とは〈クラス〉に関する法則であるのに対し,進化学ではそれが適用できない〈個物〉の学問であるという点を著者は指摘すべきではなかったか.仮説のテスト可能性はそのあとの話だ.著者は――
進化理論のユニークさは,方法論にあるのではなく,存在論にあると見なければならないと彼[Marc Ereshefsky]は結論付ける.しかし,これでは説明の放棄ではないだろうか.(p.26)
――と言う.私に言わせれば,進化学における〈個物〉vs〈クラス〉の存在論的対置を指摘した Ereshefsky の方が正しいのであって,その意味を見抜けない著者の方がまちがっていると思う.
さらに言えば,著者は進化理論の科学的地位を論じるにあたって,進化仮説のタイプ分けを怠っているように見受けられる.たとえば,自然淘汰に関する仮説(進化過程の仮説)と系統類縁関係に関する仮説(分岐図)では経験的テストのあり方は異なる.それらをひっくるめて論じることはできないはずだ.著者が文中で言及している David Hull や Robert O'Hara はその区別をしていたと私は理解している.少なくとも O'Hara が――
- Robert J. O'Hara 1988. Homage to Clio, or, toward an historical philosophy for evolutionary biology. Systematic Zoology, 37(2): 142-155.
――の中で述べた〈年代記(chronicle)〉と〈歴史(history)〉は分岐学(cladistics)の枠組みの中での対置であって,単なる〈物語り〉論を擁護しているとは考えられない.進化史の主体はクレードであり,年代記としての分岐図をまずテストし,そのあとで歴史としての進化シナリオのテストに進むべきだというのが O'Hara の基本姿勢である.科学哲学ではなく歴史哲学を見直そうという彼の宣言は,〈クラス〉を論じてきた「科学哲学」に拘泥するのではなく〈個物〉を論じる「歴史哲学」に目を向けようという大きなメッセージだと私は受け取った.あくまでも〈存在論〉をベースにしなければ,このような論議の置かれている文脈は理解しがたいと思う.
第1章を読むかぎり,現在の進化生物学に対する知識が著者には不足しているように感じられる.要所要所で〈構造主義生物学〉への言及や引用がなされているのはご愛敬としても(Brian Goodwinみたいな観念論者を引用してどーするの?とは思うが)――
第1章を読むかぎり,現在の進化生物学に対する知識が著者には不足しているように感じられる.要所要所で〈構造主義生物学〉への言及や引用がなされているのはご愛敬としても(Brian Goodwinみたいな観念論者を引用してどーするの?とは思うが)――
「進化理論は系統発生の再構築において驚くほど小さな役割しか果たしていない」というのが,偽らざるところなのである.(p.22)
――と書いてあるのには心底ビックリする.相当な〈pattern cladist〉であってもここまでは言わないだろう.もちろん,最尤法に基づく系統推定をしている人ならば,即座に〈レッドカード〉を飛び越えて〈退場処分〉を出しているはず.著者は「標準的」な進化生物学の参考書をひもとくべきだった.
著者は,「進化理論」にはさまざまなレベルのものがあって,それぞれに経験的テストのあり方が異なっているのだということがわかっていないのだろうか.進化(descent with modification)そのものも「進化理論」だし,遺伝子頻度変化という意味での自然淘汰も「進化理論」になりえる,もちろん塩基やアミノ酸の進化的置換の確率モデルだって「進化理論」,地理的分布の「進化理論」もある――そしてそれぞれの「進化理論」は程度の差は異なってもテストされ得る.自然淘汰ならば一般的な“力”の理論として〈general law〉に近い性格をもつだろう.著者は物理学など典型科学での「法則」が進化学には適用されないということから,一気に「進化理論」ではなく「物語り」だという結論にいたっているように見える.それはまちがいだと私は思う.ここでもまた著者に「標準的」な進化生物学の知識があれば,事前に回避することができる誤りは少なくなかっただろう.
進化生物学の「いま」に疎いように見受けられる著者は,本書第1章のところどころでその馬脚を露呈する.たとえば,自然淘汰を支持する研究として有名な〈工業暗化〉に関連して,著者は次のような注を付けている――
また,限られた時間的制約の中での自然選択の例として,オオシモフリエダシャクの工業暗化は有名.ただしこれについては否定的意見もある.柴谷篤弘・法橋登・斎藤嘉文編『生物学にとって構造主義とは何か』吉岡書店,1991年,51-52頁.柴谷(注3)127および145頁.Judith Hooper, Of Moths and Men(London: Fourth Estate, 2002)は,ケトルウェルらの工業暗化の証明法の杜撰さを描き出した.(p.196,注28)
――オオシモフリエダシャクの工業暗化に対する疑惑は,植物分類学者ヘズロップ・ハリソン(John Heslop Harrison)の提唱する「重金属汚染説」を踏まえている.しかし,ヘズロップ・ハリソンは常習的なデータ捏造の疑惑がもたれており,暗化を論じた彼の研究もその例外ではない(Karl Sabbagh 1999. 『A Rum Affair: A True Story of Botanical Fraud』Farrar, Strauss and Giroux, London).少なくとも,日本の構造主義生物学者たちが工業暗化への「反証」として声高に論じるほどの価値があるものかどうかは怪しい.少なくとも,学説に対して鵜呑みではなく批判的な姿勢を著者にはもってほしかった.
また,Judith Hooper の本『Of Moths and Men: An Evolutionary Tale』は,アマチュア昆虫学者H.B.D. Kettlewellと彼の師である生態遺伝学者E.B. Fordとの人間関係の叙述が中心となっている.Kettlewellの実験には確かに瑕疵があった.しかし,そういうミスを差し引いたとしても現代の研究レベルから見て「よくやった」と評価される業績である.「杜撰」と攻撃されるような致命的ミスはしていない.工業暗化に関してはその後も現在にいたるまで研究が続行されており,詳細な点で詰めが甘い箇所はあるものの,大筋では自然淘汰が野外で裏づけられた事例とみなされている.ここでもまた,著者は学説の成立経緯とその受容のあり方についてもっと慎重に論じるべきだったと私は考える.
何よりも,第1章では,〈物語り〉という口当たり(耳ざわり)のいいキーワードがその都度いろいろな意味で使われ過ぎているようだ.子どもに話して聞かせる「お話し」も歴史叙述としての「お話し」もひっくるめて,あえて【物語り(narrative)】と呼ぼうとする意図はいったいどこにあるのだろうか.
ヘイドン・ホワイトは歴史〈物語り〉論を通して相対論的懐疑論を歴史学に持ちこんだとカルロ・ギンズブルグによって繰り返し批判されてきた.日本語ではとてもやさしい語感をもつ〈物語り〉ということばは,その一方で裏口から相対主義という怪物を誘い込むダークな面をあわせもっている.著者は,ヘイドン・ホワイトの歴史観に基本的に同意しつつ――
歴史のアプローチの仕方にはっきりとした変化が見え始めるのはヘンペルに比較的近いところに位置していたアーサー・ダントの『歴史の分析哲学』(1965年)からで,1973年に『メタヒストリー』を携えたヘイドン・ホワイトの鮮やかな登場で大きく展開していくことになった.彼らの提唱するアプローチは物語り的説明である.この頃から英米の歴史学者は,もし歴史家が与える過去の説明が本物であるのなら,それは物理学に範をとる演繹的・法則的説明に近いものであるはずだとされる重荷から解放され,歴史学を科学と見るよりは人文学(アート)と見る方向に回帰し,ヘンペルやポパーの影響から徐々に脱していくことになった.(p.5)
と概観する.しかし,マイケル・ギセリンが『ダーウィン的方法の勝利』(1969年)で最初に示したように,ダーウィンから現代にいたる進化学がデータによる仮説の経験的テストをまず重視してきたことを考えるならば,歴史学に関する著者の主張はとうの昔にすでに反証されていると私は考える.歴史学はもちろん,進化学においてはなおのこと,仮説を支持する経験的基盤がどこにあるのかを問うことが不可欠である.もちろん,生物のデータは不完全である.しかしそれ自体は〈物語り〉の放恣を許すものではない.著者は本書の中で「化石は不十分」(p.25)であるため進化について十分に知ることはできないと言う.この点は著者の誤解である.系統関係にしろ進化プロセスにしろ化石以外の形質(現存生物の分子あるいは形質の情報)が生物の過去を知るための主たる情報源である.その情報を慎重に逆なですることにより,進化学者はある進化仮説がどの程度の経験的サポートを獲得できているかを相対的に評価している.この基本姿勢はヘイドン・ホワイト流の〈物語り〉論の対極にあるだろうと私は理解している.
本書の第2章以降で著者が実際に実践してきた「科学史」のケーススタディーをみるかぎり,相対主義的な色合いは薄いように感じられる.むしろ著者が引用する――
起こりえたであろうさまざまな事象を推測しながら合理的な物語りを構成する以外にない(p.19)
というグージのことばの方が本書には似合っている気がする.私が思うに,〈物語り〉というキーワードを選んだのは著者の思い違いだったのではないか.進化学も進化学史もともにデータによる仮説のテストを行なうべきだと私は考える.そして,ほかならない本書は科学史におけるテストの格好の例を与えている.本書には,〈物語り〉ではなく,もっとふさわしい〈推論(inference)〉ということばを捧げよう.著者は自らの実践として,科学史の史料を踏まえた〈推論〉を通して興味深い進化学史のエピソードを復元したのだ.本書の第2章以降の内容はそのタイトルをみごとに裏切っている――それだからこそいっそう本書は読む価値がある.
三中信宏(8/December/2003)
【目次】
はじめに v
第1章 進化論とはいかなる科学か? 1
1 科学的説明と歴史学 3
2 進化論は反証不可能か? 5
3 演繹的・法則的説明モデルとその批判 9
4 予言可能性だけに限定されない科学 14
5 進化論における物語り的説明の有効性 18
6 さまざまな批判を乗り越えて 22
第2章 生地を歩く――進化論はここで生まれた 29
1 ダウンの家とシュローズベリーの家 33
2 シュローズベリーと産業革命 36
3 チャールズゆかりの建物 41
4 マウント屋敷(The Mount) 45
5 シュローズベリー周辺の地質学調査 49
第3章 物語る『種の起源』 55
1 創世物語と博物学 57
2 リンネの楽園物語 62
3 生物の地理的分布の物語り 65
4 『種の起源』の物語り方 70
5 自然選択というメタファー 75
第4章 情動表出は進化する 83
1 ダーウィン以前の情動の考察 85
2 『人間と動物における情動の表出』執筆の経緯と前史 89
3 写真に語らせる 94
4 ダーウィンの「情動の表出三原則」 105
5 赤面について 109
6 評価――当時と今日 113
第5章 謎のコリンズ――『種の起源』に一四〇年間生き続けた男 121
1 ダーウィンの研究と育種 125
2 コリンズの登場 128
3 『家畜と栽培植物の変異』におけるコリング 132
4 コリングとその短角牛に関するダーウィンの知識の源 135
5 血統から遺伝へ 137
6 近縁交配に対する恐怖 141
7 ダーウィンとウォレス 144
8 『種の起源』の中で一四〇年生き続けた男 145
第6章 〈死の起源〉という物語り 149
1 『種の起源』と〈生物の起源〉 150
2 死を前提とする自然 154
3 死に関するヴァイスマン論文 158
4 〈死の起源〉と有性生殖 161
5 ヴァイスマン思想の英語圏への拡大 165
6 初期の批判 168
7 組織培養研究と細胞の寿命 173
8 老化と死をめぐる考察 175
付録1 ダーウィン関係の資料について 181
付録2 『種の起源』出版に至るダーウィンの事績 188
注 191
あとがき――感謝の言葉にかえて 249
初出一覧 252
図版出典一覧 [1-3]
【正誤表】
- P.129 ×「トードの『進化論辞典』にも」→ ○「トール」※ Patrick Tort は「パトリック・トール」と読むのが正しいと思われます.
- P.147 ×「CD-ROMにも,コリンズの名」→ ○「コリング」※ 前後の流れから考えて,ここは「コリング」でしょう.
- P.184 「The Writings of Charles Darwin on the Web がもっとも信頼できる」※ ウェブサイトの URL(http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/)がここで明記されるべきでしょう.
- P.208(注48) 「Peter Raby, Bright Paradise」→日本語訳あり:ピーター・レイビー『大探検時代の博物学者たち』(2000年,河出書房新社)
- P.210(注7) ×「C.E. Raven, John Ray: Naturalist (Cambridge University Press, 1950)」→○「1942」※1950年は第2版.