トリヴィア,マルジナリア,あるいは記憶の痕跡
「系統樹」ということばは、実は私たちの日常生活に深く入り込んでいる。たとえば,蕎麦屋・寿司屋・天麩羅屋でも、暖簾分けによってつながる店の系統樹が描ける。有名な江戸前の蕎麦屋(「藪」でも「砂場」でもいい)からの暖簾分けが客にアピールするのは、盛られた蕎麦を通して,その店だけでなく、蕎麦の系統樹そのものを味わいたいと客が望んでいるからだろう。食べ物だけではない。茶道や華道のような芸事にも家元の系譜がある。職場に目を向けても、コンピュータやソフトウェアに「バージョンアップ」という名の系統樹があるからこそ、ユーザーはそれらの製品の使い勝手を短期間で容易にマスターできるのだろう。
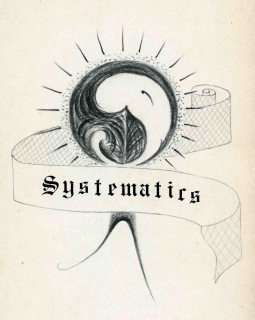
このように「系統樹」という視点でこの世の中を見渡してみると、今まで見えてこなかった隠れたつながりや系譜が背後にあるのがわかる。自然界もまた同じである。地球上の生き物の世界を「系統樹」という視点で統一的に見渡すとき、何億年もの時間を通して連綿と続いてきた生物どうしの進化的な関わり合いが見えてくる。二〇〇六年に出版した『系統樹思考の世界:すべてはツリーとともに』(講談社現代新書)では,進化するオブジェクトの時空的な「つながり」という観点から,系統樹に基づく多様性の体系化について論じた.そこでは,系統樹という図形言語は,たんに生きものの間の系統関係にとどまらず,言語や写本の類縁関係や人工物の由来関係にまで一般化できることを示した.この意味で,系統樹は自然科学から人文科学にまでおよぶ汎用性の高い情報ツールとして広く利用できる.
その気になれば身の回りにいくらでも「系統樹」が見つかるものだ.日常生活者としての私たちは,オブジェクトの多様性を効率的に理解するために,長年にわたって「系統樹」をうまく使いこなしてきたのではないだろうか.人間社会の歴史を振り返ると,想像する以上に系統樹とのつきあいは長く深いのかもしれない.系統樹は科学者の独占物ではないということだ.ものごとを整理したり体系化したりするときの汎用ツールとして系統樹思考は確かにある。
私の学問的出自は農学の一分野としての生物統計学なのだが、どういうきっかけで「系統樹」の世界に足を踏み入れるようになったのかについては多くの人が疑問に思っているらしく、ときどき訊かれることがある。しかし、実は私自身がこういう道を選ぶ契機あるいは動機が何かをうまく答えられないでいるのだ。だから、訊かれても困ってしまう。
「自分探し」ということばがある。職業としてのサイエンティストをすでに選んでしまった私は、いまになって遅ればせの「自分探し」をしているのかもしれない。科学者・研究者への道はそのときどきに遭遇した些細なできごとがきっかけになって、進むべき分かれ道を決めてきたのかもしれない。学問としての大義名分はあとからいくらでもついてくる。しかし、大学の学部から大学院にかけて、右も左もわからない中で遭遇してきたさまざまなトリヴィアが、実は自分の進む将来の方向づけを決定していたのかもしれない。それらが何だったのか、気になって夜も寝られないではないか。
私の現在の職業を訊かれれば、当然「科学者」と答える。もちろん、それで飯を食っているという意味で、科学を「生業」とするようになってからは、まだ二十年弱しか経っていない。つまり、十八歳で大学に入学し大学院を終えるまでの十年あまりは、「科学」というものに関心をもち、将来その道を進んでいこうと志してはいたのだが、どうにもこうにも金銭的収入には結びつかなかった。研究はしていたが、生業ではなかったということだ。「いつまでもそんなわけわからんことやってて、食べていけるのか」という小言のような忠告は、京都の実家に帰るたびに両親から耳にたこができるほど聞かされてきた。大学院に進みたいという奇特な学生は浮世離れしているのだという一昔前によくあった見方は、かたちを変えつつ、いまも生き残っているかもしれない。
自分の研究テーマを何とか定位できるようになったのは大学院に入ってからである。その中でさまざまな問題状況なりトリヴィアとの接近遭遇を経験したことが、あとあと考えてみれば重要な意味を持っていたということだ。
たとえ未知の分野であっても、ある程度の勉強を積めば、興味の持てそうな“知的鉱脈”に触れることがある。場合によってはそれを突き詰めることにより、自分なりの研究課題を立てることができるだろう。しかし、場合によっては、豊かな鉱脈だと思って掘り進めたら、すぐに枯渇してしまったということもあるにちがいない。しかし、一見、掘るに値しない知的トリヴィアであったとしても、それがもっと豊かな鉱脈へのポインタとなることがある。これがまたおもしろい。幸運と悲運とは紙一重である。表に露出している外見だけで中身を判断することはできないのだ。
幼いころから物事に対する私の関心の持ちようはふつうではなかったのかもしれない。妙なことや変なものにこだわり、横道やら脇道がことのほか好きで、些細なことほどむしろ価値があると思ってしまうやっかいな性格。「どんなに取るに足りないことでも一生を埋めるには十分である」。現代音楽の巨匠スティーヴ・ライヒは、作品〈プロヴァーブ〉の中でソプラノ歌手に哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインのこの独言を繰り返し歌わせている。そんなことではいけないと一念発起すべきなのか。それとも、これでいいのだと開き直るべきか。勝手に「人生訓」風に読まれてしまったヴィトゲンシュタインこそいい迷惑かもしれないが。
取るに足りない些細なことを手がかりにして秀逸な進化論エッセイを長年にわたって書き続けたのは、二〇〇二年に亡くなった古生物学者スティーヴン・グールドだった。彼が三百回にわたって『ナチュラル・ヒストリー』誌に連載したエッセイ群は空前絶後である。大学院にいた頃に、彼のエッセイ集の一冊を翻訳したことがあった(『ニワトリの歯』早川書房、一九八八年)。それぞれのエッセイの冒頭のパラグラフがとりわけ難しかったことはいまでも記憶している。科学史的な些細なことがらを出発点として一般論につなげるグールドの腕力(筆力)には心底脱帽するしかない。単発の原稿だったらひょっとしたら書けるかもしれないが、グールドのように、三十年の長きにわたって毎月書き続けられるだろうか。しかし、そのような文章術をたとえわずかでも他の科学者が身につけることができたとしたら、生物学書や進化論本の愉しみはきっと倍加するだろう。
一般に受け入れられている文学作品を読み耽るような子ども時代を送ってこなかったので、いまだに海外の(同年代の誰もが読んできたにちがいない)「名作」に関する教養を私はまるで持ち合わせていない。そういう読書のための時間はすべて野外で費やされていたからだ。小学校から中学校にかけてのことである。筋金入りの昆虫少年だった私は、これまた昆虫少年の友だちとともに、自宅近くの里山や渓流を駆け回っていた。週末ともなれば捕虫網をもって朝から山ごもりしてしまい、夜まで帰らず騒ぎになったこともあった。
一九六〇年代末から七〇年代はじめにかけては、学生運動やら高度経済成長で世の中は大きく動いていたはずだったが、南山城の山間はそういう世間のうねりやしわ寄せとはまだ無関係で、昼は渓流の石をひっくり返しては水生昆虫を集め、夜は自宅の庭でナイター(灯火採集)をしては蛾を集めるという六本足な生活が長く続いた。切手蒐集の趣味はなかったが、小学生のころからタイルや真空管そして古銭のコレクションをしていた。親戚が伏見で剥製商を営んでいた関係で、膨大な貝類の標本をもらい受けたこともあった。「蒐集」という性癖に関するかぎり、すでに十分に開花していたようだった。
対象が何であれ蒐集の経験がある人だったら誰でも思い当たるだろうが、自分が苦労して蒐集したものに対する思い入れやエピソードに際限はない。しかも、蒐集物それ自身が一種の「外部記憶装置」となって、蒐集したコレクター本人に代わってその経歴と苦労話を記憶してくれる。もちろん、ものに蓄えられた記憶を呼び出せるのは当の本人だけで、他の何人[なんぴと]も代理を務めることはできない。
思い起こせば、当時の小学校や中学校にはとんでもないコレクターが思わぬところにいた。近所の同級生の古銭マニアは、その豊富な知識といい、膨大なコレクションといい、中学生の域を超えていたと当時は思うしかなかった。あるとき彼のまねをして、寛永通宝のとある稀少アイテムを求めて京都の東山界隈を探しまわったとき、三年坂近くの骨董店の主人に「まだ中学生やのに、そういう集め方をしたらあかんで」とぴしゃりと言われたことがある。古銭の蒐集にはそれなりの作法と礼儀があったのだろうか。それとも、子どもの悪しきコレクター熱を案じての忠告だったのだろうか。何よりも、ほどなく遠くに引っ越してしまったあの彼は、当時すでに私の手の届かない達人の域にあったのだろうか。上には上があるものだ。
蒐集癖がそのまま嵩じたとしたら、ひょっとして別の人生が開けたのかもしれない。しかし、中学卒業後,一九七三年の春に宇治市にあった府立城南高校に進学した後は(その高校は二〇〇九年春に近隣校との統合により「校名」の痕跡のみ遺してみごとになくなってしまったが)、コレクターとしての人生は表舞台から退き、一見ふつうのしかしけっして平均的ではない高校生活を送ることになる。しかし、私の蒐集癖とこだわりが消えたわけではけっしてなかった。その欲望はかたちを変え、そして別の標的を求めただけだった。
マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』にこんな一節がある。
過去を思い出そうとつとめるのは無駄骨であり、知性のいっさいの努力は空しい。過去は知性の領域外の、知性の手の届かないところで、たとえば予想もしなかった品物のなかに(この品物の与える感覚のなかに)潜んでいるのだ。私たちが生きているうちにこの品物に出会うか出会わないか、それは偶然によるのである。(マルセル・プルースト〔鈴木道彦訳〕『失われた時を求めて1・第一篇:スワン家の方へ』集英社、一九九六年, p. 108)
主人公の「私」にとってその「予想もしなかった品物」とは、紅茶に浸したプチット・マドレーヌだった。「私」がそのマドレーヌを口にしたとたん、失われていたはずの過去の記憶が霧が吹き払われるようによみがえり、長大な物語が語られ始める。フランス音楽で言えば、モーリス・ラヴェルの佳品〈ラ・ヴァルス〉で、冒頭の靄か雲がかかったような幻想的雰囲気が吹き払われて、眼下の円舞場の華やいだ情景がくっきりと大映しになってくるあの感覚だ。
本を読むときの癖は人によっていろいろだ。私の場合は、昔から傍線を付けたり、周囲にいろいろ書き込みをしたり、あるいは付箋紙を幟のように立てながら読む癖があった。そのような「マルジナリア」の落書は、読んでいる最中はもちろん自分にとっての備忘メモであるわけだが、いったん読んでしまった後は過去の読書記録としていつまでも残ることになる。言い換えれば、マルジナリアのない“まっ白”なページの本はまだ読まれていない本か、もしくは読んだことは読んだのだが記録されなかった本ということになる。
記録がなければ記憶はすぐに揮発してしまってもう取り返しがつかない。記録があればたとえ記憶が失われてもそれを復元することは難しくない。
小説のたぐいを読んだときは記憶が薄れても実害はないのだが、自分の仕事に直結するあるいは興味のある題材に関わる本の場合は、最初からマルジナリアをしっかりつくりこみながら読むにかぎる。たとえ、読み終わってから年月が過ぎ、その本についての記憶が失われたとしても、残されたマルジナリアを見れば、それを読んだ当時の自分のありさまを復元することは容易である。それだけでなく、その本に関わるあるいはそれを読んでいた頃の自分に関わるさまざまなことどももきっとよみがえってくるだろう。それは場合によっては「私」が経験したような予期せざるとまどいや驚きを伴っているかもしれない。
遺伝学の始祖であるモラヴィアの修道士グレゴール・メンデルは、十九世紀半ばに自ら修道院の庭でエンドウマメの交配実験を行い、その理論的な考察を『雑種植物の研究』と銘打って同地の博物学会誌に発表した。自然科学者にとって、今も昔も変わらない厳然たる掟は、研究発表のメディアはできるだけメジャーでなければならないということだ。当時のチェコで発行されたこの学会誌はその意味でメンデルの論文を載せる媒体としてふさわしい雑誌では必ずしもなかった。実際、彼の遺伝学研究が半世紀近くも忘れ去られてしまった一因は、発表誌がマイナー過ぎたからだった。
メンデルは発表した論文の自分用の別刷をもっていて、そのマルジナリアには彼自身による遺伝法則の考察に関するメモ書きがあったそうだ。しかし、その別刷のマルジナリアは、メンデルの死後、製本されるときに裁断によって裁ち落とされてしまい、永久に失われることになった。
一方、現代進化学の基礎を築いたチャールズ・ダーウィンの場合は、彼の研究や著作に関わる資料がしっかり保存されていて、『種の起源』に先行するノートブック類はもとよりちょっとしたメモにいたるまでくまなく研究されている(しかもそのほとんどは現在インターネット公開されている)。「ダーウィン産業」という看板はだてではない。もちろん、ダーウィンのマルジナリアも詳細に研究されていることは言うまでもない。
マルジナリアは、パーソナルであるがゆえにかけがえのない価値があり、ちょっとした運命のいたずらで(あるいは必然的な理由により)、はかなく失われてしまったり、後世に伝えられたりする。運よく生き残ったトリヴィアに幸あれ。マルジナリアは他人にとってはトリヴィアであっても、当の本人にとってはマドレーヌだったりする。
メンデルやダーウィンという巨人の名前をいったん出してしまったあとで、自分の話に戻るのはとても気が引ける。しかし、この連載では、自分の昔話をすることが目的ではない。私はまだそんな年ではないからだ。むしろ、自分のこれまでのマルジナリアをしばし振り返ることにより、いまの私が興味をもっている対象への系譜的つながり、そして地球とその生物界に取り組んできた先駆者と彼らが考えたこと、そしてサイエンスそのものに結びつけていきたい。
大学に入学してさまざまな教科書を買ったが、それは半ば強制だった。駒場キャンパスにいた頃はその意味ではあまり自由度がなかったのかもしれない。一学年三千人も学生がいればその多くは平均値のまわりにひしめくというのは統計学的な真理だろう。しかし、そういう大多数の集団から抜け出る俊英は今も昔も光り輝く。ノーム・チョムスキー流の生成文法学者として“天才”の名をほしいままにした東大文学部言語学科の故・原田信一(一九四七〜七八)は、高校生の頃からタバコ屋の二階に下宿しつつ、世界中の著名な言語学者たちに論文別刷請求の手紙を出し続けたという。請求された相手はてっきり日本の新進気鋭の若手教授から届いた論文リクエストだとそろって勘違いしたそうだ。
この印象的なエピソードを私が読んだのは、駒場から本郷に進学し、農学部三年に在籍していた一九七九年のことだった。将来を嘱望されていた原田は前年一九七八年に三十歳で衝撃的な自殺を遂げ、翌年、雑誌『言語』に彼の追悼特集が編まれた。そこに載った記事のひとつがそれだったと記憶している。もう三十年近くも前のことなのに、不思議と記憶から揮発せずに残り続けている。農学部にいた私はなぜ毎月『言語』やいまは亡き『言語生活』などの月刊誌を欠かさず購読していたのだろうか。それもまた私にとってのマドレーヌの一つであることはまちがいない。しかし、残念なことに、私の記したマルジナリアが残っていたかもしれないそれらの雑誌のバックナンバーは、いつしか処分されて消えてしまった。
いまもある東大特有の進学振り分け制度のおかげで、駒場での最初の二年間はあせって専門化することなく過ごすことができた(それゆえ留年率も高かったのだが)。しかし、本郷に進む三年生以降は将来のことを否が応でも考えないわけにはいかなくなる。発生生物学者コンラッド・ウォディントンが提唱した「運河化(キャナリゼーション)」の理論が生物の発生過程の分岐的決定を記述したように、大学に入った最初のうちは自由に活動できるしくみになっていても、学年を追うに従ってしだいに動ける範囲が狭くなっていく−という漠然とした閉塞感があったことは個人的にはあてはまっていたのだろう。駒場の生物の先生だった畑中信一教授のドイツ語生物学輪講というセミナーに出てみたり、必修ではない第三外国語をとろうとしてみたり、あるいは言語学系の雑誌を読んでみたりしたのは、ひょっとしたらそういう閉塞感の裏返しだったのかもしれない。
研究室や自宅にある本だなにはそういう過去の記憶をひきずった本たちが今もたくさん眠っている。とりわけうしろの本だなや本だなのうしろには、もう何年もひもといていない(しかし昔はしっかり読んだはずの)古参の本たちがひっそりと並んでいる。いま私があるのは彼らのおかげかもしれない。そして、ほこりをふっと吹き払って久しぶりにページをめくったとたん、「そのとき一気に、思い出があらわれた」(前掲『失われた時を求めて』,p. 112)。