【書名】磁力と重力の発見(全3巻).第3巻――近代の始まり
【著者】山本義隆
【刊行】2003年05月22日
【出版】みすず書房,東京
【頁数】第3巻――vi, 605-947, 79 pp.
【定価】第3巻――3,000円(本体価格)
【ISBN】第3巻――4-622-08033-8
【備考】全巻構成と詳細目次
<http://cse.niaes.affrc.go.jp/minaka/files/physics-history.html>
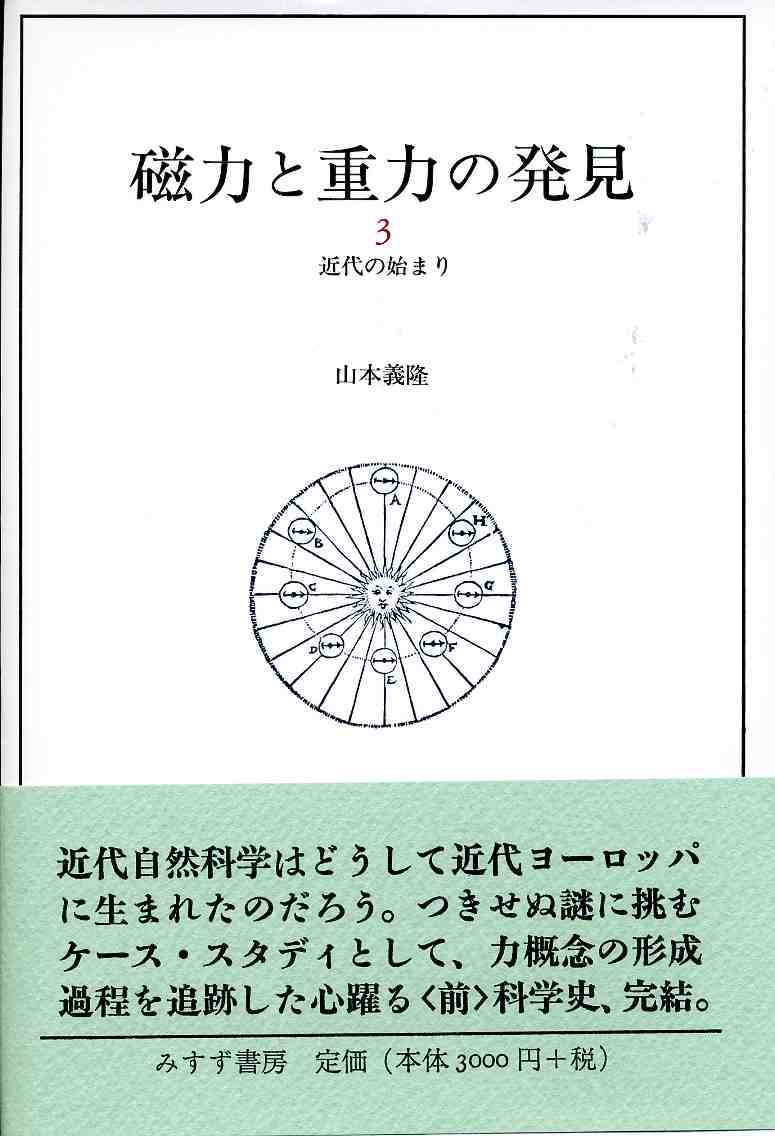
【概略目次】
――第3巻――
第17章:ウィリアム・ギルバートの『磁石論』 605
第18章:磁気哲学とヨハネス・ケプラー 673
第19章:十七世紀機械論哲学と力 735
第20章:ロバート・ボイルとイギリスにおける機械論の変質 775
第21章:磁力と重力――フックとニュートン 820
第22章:エピローグ――磁力法則の測定と確定 880
あとがき 939
注 [65-79]
文献 [24-64]
索引 [1-23]
【書評】※Copyright 2003 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
近代の「力」観念史をたどる第3巻は,ウィリアム・ギルバートの〈磁気哲学〉で幕を開ける.第17章は,ギルバートの『磁石論』(1600)とその影響の広がりを論じる.彼の功績のひとつは,磁気学と電気学を分離した上で,包括的自然観としての〈磁気哲学〉(p.614)を提唱した点.しかも,それが機械論ではなくむしろ物活論に近い立場であることだと著者は言う(p.669).続く第18章では,ヨハネス・ケプラーの天文学に目を向ける.やっと磁力と重力の主役が出てくる予感がする.ギルバートの磁気哲学の影響を受けたケプラーは星の運動もまた遠隔作用による力の影響を受けており,磁気作用と同じだろうという推論である(p.696).そして,重力を明らかにするための「数学的関数」を編み出す.
しかし,重力の数学的定式化を試みたケプラーの精神は,次の世代には引き継がれなかった.第19章は,デカルトとガリレオの〈機械論〉に光を当て,遠隔作用を否定する機械論がケプラーの意図をつかみ損ねた経緯をたどる.デカルトが遠隔作用を近接作用によって説明するために編み出したさまざまな憶説(エーテル体説や渦動仮説など:p.750)は,ことごとく失敗し,磁力を近接的に説明するための「施条粒子説」にいたっては空論そのものだった(p.764).第20章では,フランシス・ベーコンに始まるイギリスの経験主義をとりあげ,デカルトの機械論が経験主義の土壌で変容していくようすが考察される.言説はデータに基づいてその真偽が判定されるということだ.ロバート・ボイルがこの立場を代表する科学者として登場する.
ピント-コレイアの『イヴの卵』でも,発生学における「前成説/後成説」論争の中で,同様の議論が展開される.時代的にも同じ17世紀,胚は卵の中で機械論的に後成されるという主張はその形成力の荒唐無稽ぶりが結果として前成説に利したという歴史的事実が思い浮かぶ.
続く第21章は,王立協会の創立とともに,経験主義に則った〈実験哲学〉がイギリスに浸透していく過程を論じる.ロバート・フックやアイザック・ニュートンは,近接作用としてではなく,ふたたび遠隔作用として磁力と重力をとらえなおした.重要なことは,問題設定のスタイルそのものを変え,「〜とは何か」という存在論的設問(本質と原因への問いかけ)を放棄し,「〜はどのように作用するか」という法則性の定量的解明を解決すべき問題としてセットした(pp.850-860).力の法則性を解明することで,〈魔術〉的性格をもっていた遠隔力は合理化されたのだと著者は言う(p.862).重力に関する遠隔作用論はこのようにして経験科学の中に着地した.
最後の第22章は,磁力の法則性解明と遠隔作用解釈の定着についてである.18世紀に入り,ヨーロッパ大陸で進められた磁力の測定実験を通じて,重力と同様に,その法則性が解明されていった.この経緯を振り返って著者はこのように要約する:「物理学は事物の本質についての形而上学的な認識を求めることを放棄し,さしあたって現象の法則についての数学的な確実性を求めることに自足したのである.そしてここに数理物理学がはじまる」(p.935).
「力」概念の発展史から言えることは,遠隔作用を否定したデカルト的機械論は結果として敗退し,対立する自然魔術的な物活論が近代物理学を生みだした母体ということである.魔術が確かに近代科学の成立に寄与したことは事実であり,それを過小評価したり,逆に過大評価することを戒めつつ,本書全体が締めくくられる.
ローカルな科学における概念形成史をケーススタディとして追求した本書は,単に物理学史の書物というだけにとどまらず,もっと一般的な「自然思想史」とみなされるべきだ.物理学のたどってきた道を生物学のそれと比較してみると,両者のちがいは明白だろうし,そのちがいが何に由来するのかを探るのはきっと本書と同じ1000ページの本を要求するだろう.存在の学としての形而上学は,なぜ物理学では〈無害化〉できたのか,それにひきかえどうして生物学では形而上学が〈野放し〉のままなのかを問いかけることは意味のあることだろうと思う.クラスと個物のちがい? それとも,歴史上の偶然?
現代物理学では不問に付された形而上学は果たしてこのまま休眠し続けるのかという問題意識をもちつつ,本書を多くの読者に勧めたいと思う.文句なくいい本だから.ほらほら,読みなさい.さもないと遠隔操作してしまうぞ!