【書名】Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages
【著者】Daniel Nettle and Suzanne Romaine
【刊行】2000年
【出版】Oxford University Press, Oxford
【頁数】xii+241pp.
【価格】US$ 19.95
【ISBN】0-19-513624-1 (hardcover)
【訳書】『消えゆく言語たち:失われることば,失われる世界』
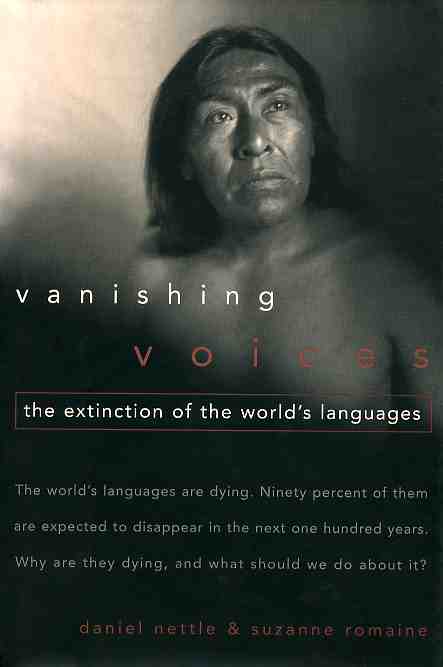
【書評】※Copyright 2000 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
ある言語はどのようにして死んでいくのか、その背景と原因は何か、ある言語を守るためにはどのようにすればいいのかを具体的事例を通じてたどることが本書の目的である。
本書では、現在の地球に見られる言語の多様性を、生物の多様性と一体化させて、【生物言語多様性】(biolinguistic diversity: p.ix)という新たな観点から論じていることが注目される。実際、本書を読み進んでいくと、生物多様性と積極的に絡めることにより、言語多様性の危機とその保全を進めるという姿勢がはっきり読み取れる。保全生物学に関心のある読者ならば、本書に構想されている【保全言語学】のビジョンを容易に理解することができるだろう。序文の中で著者たちは述べている:
「言語の絶滅は、世界的規模での生態系全体の崩壊というもっと大きな図式の一部分である。われわれの調査によれば、地域的な生物多様度と言語多様度とのあいだには驚くべき相関が見られる、このことは“生物言語多様性”−すなわち、地上の動植物種すべてを含み、さらに人間の文化と言語をも包括する豊かな広がり−と呼ぶべきものを一括して保全するという議論を可能にする。」(p.ix)
言語系統樹を構成するひとつひとつの言語は、「話者がたった一人になった」時点で事実上絶滅し、その最後の話者が死んだ時点で完全に絶滅する。第1章は、世界各地から集められた、このような「last speakers」の記録から始まる:
- Manx語(マン島)の最後の話者 Ned Maddrell−1974年死亡
- Ubykh語(コーカサス)の最後の話者 Telvic Esenc−1992年死亡。
- Catawba Sioux語(北米)の最後の話者 Ted Thundercloud−1996年死亡。
- ...
言語の多様性は文化の多様性と一体であるから、言語の絶滅は文化の絶滅にほかならない。しかも、地域的な文化はそれを担っている人間社会とともにその地域の生物学的環境と一体化して考えるべきである。ところが、生物の絶滅に対しては社会的な関心が高いのに、言語の絶滅はそれほどの注目を集めることがない。両者は密接に連動しているという事実を周知させる必要がある−著者たちが“生物言語多様性”という概念を提唱する理由はここにある(p.13)。
事実上の“lingua franca”としての英語のもとで(p.17)、多言語主義(multilingualism: p.18)へのさまざまな圧力は決して小さくない。そこには言語の経済学的価値とか民族的・政治的環境など単純ではない背景があることは確かだが、6000もの言語を200ほどの国で話しているのだから、多言語主義は当然のことではないかと著者らは言う(p.21)。
第2章では、言語多様性を世界的に概観する。地理的に見ると言語多様度は均一ではなく、とりわけ熱帯雨林(東南アジア・アフリカ・中米)での言語多様度の高さが突出している(p.32)。生物多様度に関する“hotbeds”地域が言語多様度にもそのまま対応するいう事実は、“生物言語多様性”という統一的な観点からの見直しを要求する。著者らは、「言語は、種と同じく、環境に対して高度に適用している」(p.43);「種と同じく、言語もまた生態学的ニッチを占有していると考えられる」(p.45)と生物と言語との並行性を強調する。
続く第3章は、言語の「死に方」に目を向ける。1815年の火山噴火により話者全員が死んだため、言語として消滅した Tamboran 語(インドネシア)のような突然死の例外を除けば、一般的に言語は話者集団が小さくなったり、しだいに使われなくなったりして、ゆっくりと死んでいく(p.51)。ある言語が死ぬことで、いったい何が喪失されるのか? 著者らは、地域的知識、民俗分類、そして認知体系の三つが言語の絶滅とともに失われると指摘する(pp.56-69)。要するに、【現地の言語】(indigenous language)がなくなれば【現地の知識】(indigenous knowledge)もそれとともに失われるのである(p.71)。
第4章は、言語が人間社会の中でどのような「生態」をしているかを論じる。言語の「生き方」を見ることで、その「死に方」にも光が当てられるだろう。生物言語的に地球上でもっとも多様なパプア・ニューギニアで、言語がどのように分化していったのかを考えると、環境としての生産性の高さ・高地による地理的な隔離・部族間の戦いの三つが原因として挙げられる(pp.84ff.)。著者らはニューギニアは「言語平衡」(linguistic equilibrium: p.89)−分化する言語と絶滅する言語との平衡状態−にあるとみなしている。
言語が「死ぬ」原因は、話者がいなくなるか、または言語の移行−政治的に言語の放棄を強制されるケースと社会・文化的制約のもとで自発的に別言語に移行する−が生じたかのいずれかである(pp.90-91)。また、言語が「死ぬ」までの経緯にも:
- 「トップダウン死」−ある言語が社会・学校・政府などの公的機関で使用されなくなり、家族のような私的なネットワークだけに使用が限定されて死んでいくこと。[スコットランドのゲール語とかフランスのブルトン語など]
- 「ボトムアップ死」−ある言語が家族・知人・日常生活でしだいに使われなくなり、公的かつ形式的な場でのみ使われながら、言語として死んでいくこと。[ラテン語など]というちがいがある。
本書の後半は「社会言語学」的な記述に重点が置かれる。この分野では、すでに日本語で読める著作が多くあり、『地球語としての英語』(D.クリスタル著,みすず書房,1999年)は、現在“the global village”の事実上の“lingua franca”となっている英語の観点から言語使用の問題について論じたものである。またヨーロッパにおける少数言語の現状を概観した『現代ヨーロッパの言語』(田中克彦・H.ハールマン著,岩波新書[黄292],1985年)、そしてアメリカ・インディアンの絶滅[危惧]言語を記録した『滅びゆく言葉を追って』(青木晴夫著,岩波・同時代ライブラリー331,1998年)と『イシ:北米最後の野生インディアン』(T.クローバー著,岩波・同時代ライブラリー)は、本書“Vanishing Voices”とほぼ重なるテーマを軸として書かれている。
ただし、私の読後感では、【言語】を【生物】と同列に扱い、“生物言語多様性”という統一的視点から論じたという点で、“Vanishing Voices”には類書とは異なっているようだ。本書を読んだ保全生物学者が、その論議の進め方や視点に対して多少なりとも親近感を抱くとしたら、本書の著者たちの基本的主張は外れてはいなかったということになるだろう。
さて、第5章は、農耕技術をもった民族が採集最終狩猟民族と接したときに生じた生物言語多様性の喪失を論じる。採集狩猟社会では言語は分化するが(p.103)、いったん農業をもった民族が外から到来すると、その民族の言語に同化してしまうケースが多い(p.110)と著者らは指摘する。実際、農耕技術の「波」が押し寄せてこなかった地域−東南アジア・アフリカなど−では、言語多様度が高く維持されていると言う(p.125)。この章については、J.ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(草思社,2000年)に詳述されている内容が参考になる。
第6章のテーマは、農業の「波」と連動して押し寄せてくる、経済の「波」が言語多様度に与えた影響である。言語が失われる大きな要因の一つは、話者コミュニティによる「言語シフト」である。本章では、言語シフトの要因として、経済の「波」の影響を挙げる。使用言語が、話者の経済的ランクと連動するとき、優位に立つ「メトロポリタン言語」とそれ以外の「周辺的言語」という差異が生じる(p.128)。その結果、メトロポリタン言語への同化による言語多様度の喪失が見られる。実例として挙げられているのは、ヨーロッパのケルト語群の年代的退潮である(pp.133ff.)。
続く第7章では、「なぜ生物言語多様性を保全しなければならないのか?」という疑問に答える。著者らは、言語の衰退は放置してもかまわないとする【傍観派】(benign neglect: p.153)を批判することにより、この疑問に答えようとする。典型的な傍観派は:
- 言語は人間がコントロールできないシステムである
- 言語を選ぶのは経済的規準に基づく話者の自発的選択の結果である
- 先進国が発展途上国の言語状況に口出しすることは僭越である
著者らは、この傍観派の主張に対し、話者による言語選択は決して自発的ではなく、むしろ経済的に追い込まれた上でのことである点を指摘し、言語多様性と経済的発展とを両立させる道があり得ると反論する(pp.154-155)。すなわち、sustainable development を実現する「唯一の方法は、われわれの行動を変革することである」(p.158)と言う。どのように変えればいいのか?−それは「現地の知識体系」の有効利用にほかならない(p.166)。ローカルな環境を熟知しているのは、そこに長年にわたって生活してきた現地人であり、それは現地語でコード化された知識体系に表現されている。民族分類学の古典的事例として有名なフィリピンの Hanunoo族などの知識体系を例に取りつつ(pp.166ff.)、著者らは、現地語を「自然資源」として保全することは、現地の知識体系を守り、ひいては現地の社会・文化・生態系の sustainable な発展につながると主張する(p.170)。ただし、これを実現する前提としては、中央集権ではなく、ローカルな社会の自己決定権(「言語権」をも含む)を尊重することが肝要である(p.172)。
最後の第8章では、第7章に述べられた保全言語学の基本方針を実際に推進しているケーススタディーが挙げられている。言語保全は家庭を舞台とする【ボトムアップ】施策と自治体が主力となる【トップダウン】施策の二通りがあるが、著者らはまず初めに草の根(ボトムアップ)的な運動を推奨する(p.177)。ハワイ、ブラジル、そしてアメリカインディアンの言語保全運動を例に挙げながら(pp.179-186)、言語保全に伴う具体的問題点を示した上で、最後は多言語主義(multilingualism)と多文化主義(multiculturalism)こそ[通念に反して]普通のことなのだという結論を導く:
[O]ur global village must be truly multicultural and multilingual, or it will not exist at all. (p.204)
生物多様性と言語多様性の保全とをタイアップして考えている点で、本書はユニークであり、保全生物学に関心をもつ読者にとってもきっと興味深い読み物になると思われる。本書全体にわたり、文章はしごく明快であり、煩瑣な引用は極力避けられている。保全言語学に関する背景知識がなくても、本書はまったく問題なく読めるだろう。いい本だと私は感じた。
【目次】
List of illustrations vii
Preface ix
1. Where have all the languages gone? 1
Why and how are languages dying? 5
Where and when are languages at risk? 7
Why worry about languages dying? 10
What van be done? 23
2. A word of diversity 46
How many languages are there and where are they spoken? 27
Hotbeds of linguistic diversity 33
Endangerment: the extent of the threat 39
Biolinguistic diversity: some correlations between the
linguistic and biological worlds 41
3. Lost words / lost worlds 50
Sudden versus gradual death 51
What happened in gradual death? 53
What is being lost 1: a rose by any other name? 56
What is being lost 2: what's mine is mine? 62
What is being lost 3: women, fire, and dangerous things 66
Lost languages, lost knowledge 69
4. The ecology of language 78
Babel in paradise: Papua New Guinea 80
Why are there so many languages? 84
The ways languages die 90
What has changed 97
5. The biological wave 99
The Paleolithic world system 101
The Neolithic revolution 104
Different trajectories after the Neolithic 111
The Neolitrhic afterschock 114
The untouched world 124
6. The economic wave 126
The rise to dominance 128
Economic takeoff 131
First casualties: the Celtic languages 133
The spread to the developing world 143
Double dangers 147
7. Why something should be done 150
Why bother 153
Making choices 154
Language, development, and sustainability 155
Indigenous knowledge systems 166
Language rights and human rights 172
8. Sustainable futures 176
Bottom-up approaches to language maintenance:
some case studies 177
Settling for less, but getting more? 186
Who's afraid of bilingualism? 190
Living without a heart 193
Planning for survival: languages as natural resources 199
Some top-down strategies 200
References and furthur reading 205
Bibliography 215
Index 225