【書名】磁力と重力の発見(全3巻).第2巻――ルネサンス
【著者】山本義隆
【刊行】2003年05月22日
【出版】みすず書房,東京
【頁数】第2巻――vi, 305-604, 18 pp.
【定価】第2巻――2,800円(本体価格)
【ISBN】第2巻――4-622-08032-X
【備考】全巻構成と詳細目次
<http://cse.niaes.affrc.go.jp/minaka/files/physics-history.html>
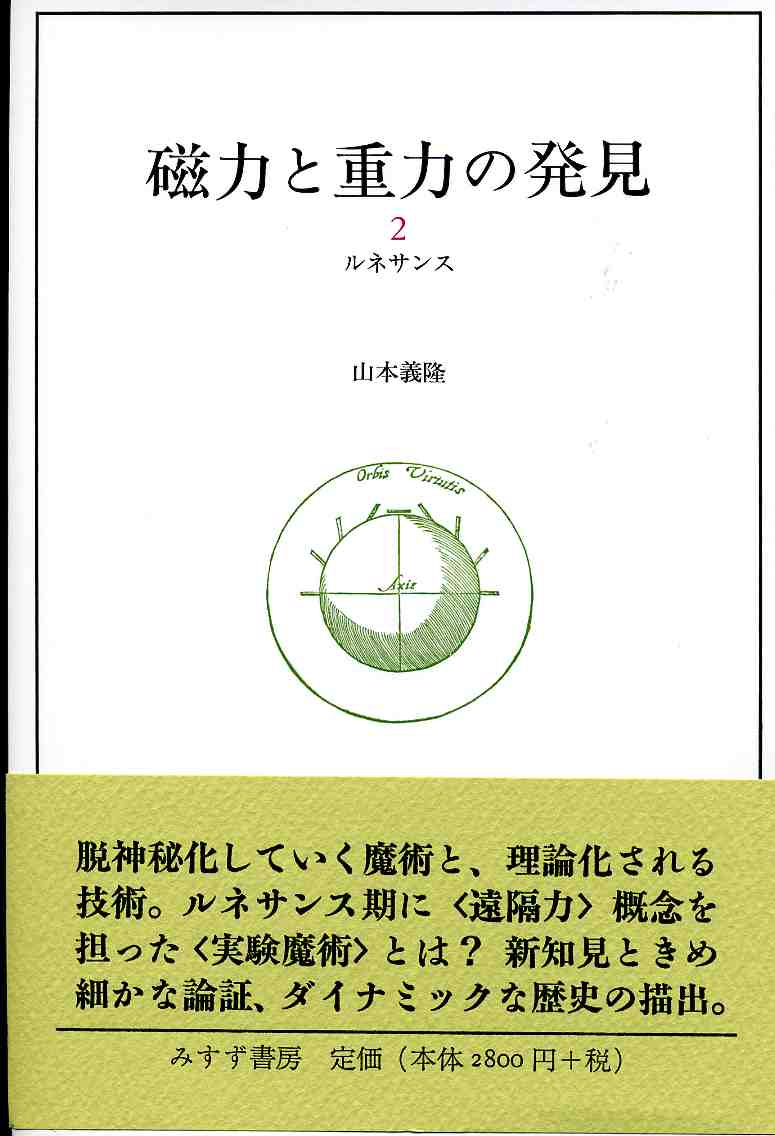
【概略目次】
――第2巻――
第9章:ニコラウス・クザーヌスと磁力の量化 305
第10章:古代の発見と前期ルネサンスの魔術 333
第11章:大航海時代と偏角の発見 372
第12章:ロバート・ノーマンと『新しい引力』 412
第13章:鉱業の発展と磁力の特異性 444
第14章:パラケルススと磁気治療 481
第15章:後期ルネサンスの魔術思想とその変貌 510
第16章:デッラ・ポルタの磁力研究 559
注 [1-18]
【書評】※Copyright 2003 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
第2巻は〈魔術〉が中心テーマとなる.「魔術」と聞いて後ずさりする読者はきっと少なくないだろう。しかし,この巻こそ,全体の中でもっとも刺激的かつおもしろいと私は感じる.いわゆる〈暗黒の中世〉からルネサンスを経て,近代の科学に連なる系譜を考えるとき,さまざまなタイプの〈魔術〉とよばれる「技芸」があったわけで,著者はその中でも遠隔作用としての「磁力」は〈魔術〉そのものであったことを指摘する.しかも,〈魔術〉の発展とともに進んできた「実験的手法」と「経験的思考」は,その後の近代科学が育つ揺籃であったことを著者は示す.
第9章は, 15世紀のニコラウス・クザーヌスにおける「力」概念の大きな転換を跡づける.中世とルネサンスの境目に位置するとされるクザーヌスは,いろいろな意味で「中世的なもの」と「ルネサンス的なもの」の混淆を体現していた.後世に影響を与えたクザーヌスの思想の中でも,とりわけ「数的思考の重視」(pp.316ff.)に注目したい.磁力についてもクザーヌスは「測る」ことが大事だと言う(p.327).磁力を操ることが当時の「魔術」のひとつであったとすると,磁力の定量的測定を行なったクザーヌスは,一般の読者が思いこんでいる「魔術」とは異なるタイプの営為をしていたことになる.それが後の章の中心テーマのひとつとなる〈自然魔術〉である.
第10章では,この〈魔術〉に光を当てる.ルネサンスにおける〈魔術〉の復権は,人間が自然を支配できるとみなすルネサンスの人間中心主義の精神のもうひとつの発露であると著者は言う(p.343).もちろん,もともとの〈魔術〉は超自然的な霊(ダイモン)によるとみなされる行為だが,クザーヌス以降,そのような〈ダイモン魔術〉とは別個の〈自然魔術〉が登場してくる(p.348).著者はこの〈自然魔術〉がその後の科学に与えた影響を「力」概念の史的検討を通して調べる.遠隔力という〈隠れた力(virtus occulta)〉をあやつるという点では同一であっても,宗教的な〈ダイモン魔術〉と定量的な〈自然魔術〉とは異なっている(p.370)という著者の主張は,その後の章でも繰り返し述べられる.
定量的精神は測定および経験という実践的行為をともなう.自然魔術が対象とした磁力は,ちょうど同期する「大航海時代」に実践的な技法として要求された.それは航海にとって必要な羅針盤の製作に関連していた.第11〜12章では,磁針の「偏角」と「伏角」現象の発見を取り上げ,一般の船乗りや職人あるいは市民がどのようにして科学(自然魔術)の裾野を広げていったのかを展望する.この視点は,続く第13章でさらに敷延される.印刷術の発明と俗語による科学書の普及が,16世紀において一種の「文化革命」の様相を呈していると著者は言う(この指摘は科学史的におもしろい).ピリングッチョの『ピロテクニア』(1540)やアグリコラ『デ・レ・メトリカ』(1556)のような浩瀚な科学技術書が広く受け容れられるようになった事情を探る.第14章の「武器軟膏」の話(p.504)はちょっと無気味で〈魔術〉的.それだけに,遠隔作用が〈魔術〉の十八番だったことをうかがわせる.
第15章では,ルネサンス後期の自然魔術を論じる.〈隠れた力〉も最終的には自然的原因に帰着されるのであって,ダイモンのような超自然的原因をもちだすのはまちがっているという見解(p.517)は,「自然主義的で技術的な魔術観」(p.524)をもたらす.現代の多くの読者にとっては,「魔術」と「科学」の並列は違和感がぬぐえないが,本書でいう〈自然魔術〉はほとんど【実験科学】と同義であるといってよいだろう.実際,オカルトが単に「隠れた」という意味しかない(そこに超自然的な含意はない)とき,隠れた作用を明らかにするのは,論理的な演繹ではなく,実験・測定を踏まえた帰納に頼るしかないだろう.
欲を言えば,ここでも中世の形而上学(存在論)との関わりに言及があってほしかった.なぜ「本質」を求める実念論的姿勢が中世のスコラ学に広まっていたのか.対立する唯名論の立場はどうだったのかとか.アリストテレス的な演繹主義が本質主義をベースにしていたことは事実だろうし.いずれにせよ,演繹的なスコラ学と超自然的な〈ダイモン魔術〉を両極端としたとき,非演繹的でしかも実験に基づく〈自然魔術〉がその内分点に位置するという著者の主張は説得的だ.
第16章は,デッラ・ポルタのベストセラー『自然魔術』(1558)をとり上げる.タイトルとは裏腹に,ほとんど「博物誌」に近い内容をもつとされる本書は,「思弁的な文献魔術から実証性を重んじる実験魔術への転換」(p.571)を遂げたという点で画期的な書物であり,とくに,デッラ・ポルタの磁石研究は後世の歴史家がことごとく見逃してきたが,その内容は続く時代の先鞭をつけたものにほかならないと著者は言う.
Accademia Linceiの歴史をたどったDavid Freedman『The Eye of the Lynx』では,アカデミアの創始者であるFederico Cessiが数歳年上のデッラ・ポルタに心酔していたと書かれている(同書,p.72).Academia Linceiがオオヤマネコ(lynx)を自然研究のイコンとして用いたのは,先行する『自然魔術』の扉絵(p.569,図16.2)に同じくオオヤマネコが描かれていたこととも関係するのかな.
この章の終わりの部分で,著者は〈魔術〉と〈科学〉のちがいをまとめている(pp.599ff.).〈魔術〉の秘匿性に対する〈科学〉の公開性という対比は,実はそれほど正確ではなく,むしろ初期段階では〈魔術〉も〈科学〉もともに公開性と秘匿性を併せもっていたと考えるべきだろうと著者は言う(p.601).科学の裾野が広がるにつれて,出版や教育を通じて秘匿性がしだいに消失し,世俗的になっていったというのが著者の意見である.
第15章では,ルネサンス後期の自然魔術を論じる.〈隠れた力〉も最終的には自然的原因に帰着されるのであって,ダイモンのような超自然的原因をもちだすのはまちがっているという見解(p.517)は,「自然主義的で技術的な魔術観」(p.524)をもたらす.現代の多くの読者にとっては,「魔術」と「科学」の並列は違和感がぬぐえないが,本書でいう〈自然魔術〉はほとんど【実験科学】と同義であるといってよいだろう.実際,オカルトが単に「隠れた」という意味しかない(そこに超自然的な含意はない)とき,隠れた作用を明らかにするのは,論理的な演繹ではなく,実験・測定を踏まえた帰納に頼るしかないだろう.
欲を言えば,ここでも中世の形而上学(存在論)との関わりに言及があってほしかった.なぜ「本質」を求める実念論的姿勢が中世のスコラ学に広まっていたのか.対立する唯名論の立場はどうだったのかとか.アリストテレス的な演繹主義が本質主義をベースにしていたことは事実だろうし.いずれにせよ,演繹的なスコラ学と超自然的な〈ダイモン魔術〉を両極端としたとき,非演繹的でしかも実験に基づく〈自然魔術〉がその内分点に位置するという著者の主張は説得的だ.
第16章は,デッラ・ポルタのベストセラー『自然魔術』(1558)をとり上げる.タイトルとは裏腹に,ほとんど「博物誌」に近い内容をもつとされる本書は,「思弁的な文献魔術から実証性を重んじる実験魔術への転換」(p.571)を遂げたという点で画期的な書物であり,とくに,デッラ・ポルタの磁石研究は後世の歴史家がことごとく見逃してきたが,その内容は続く時代の先鞭をつけたものにほかならないと著者は言う.
Accademia Linceiの歴史をたどったDavid Freedman『The Eye of the Lynx』では,アカデミアの創始者であるFederico Cessiが数歳年上のデッラ・ポルタに心酔していたと書かれている(同書,p.72).Academia Linceiがオオヤマネコ(lynx)を自然研究のイコンとして用いたのは,先行する『自然魔術』の扉絵(p.569,図16.2)に同じくオオヤマネコが描かれていたこととも関係するのかな.
この章の終わりの部分で,著者は〈魔術〉と〈科学〉のちがいをまとめている(pp.599ff.).〈魔術〉の秘匿性に対する〈科学〉の公開性という対比は,実はそれほど正確ではなく,むしろ初期段階では〈魔術〉も〈科学〉もともに公開性と秘匿性を併せもっていたと考えるべきだろうと著者は言う(p.601).科学の裾野が広がるにつれて,出版や教育を通じて秘匿性がしだいに消失し,世俗的になっていったというのが著者の意見である.