【書名】磁力と重力の発見(全3巻).第1巻――古代・中世
【著者】山本義隆
【刊行】2003年05月22日
【出版】みすず書房,東京
【頁数】第1巻――vi, 1-304, 20 pp.
【定価】第1巻――2,800円(本体価格)
【ISBN】第1巻――4-622-08031-1
【備考】全巻構成と詳細目次
<http://cse.niaes.affrc.go.jp/minaka/files/physics-history.html>
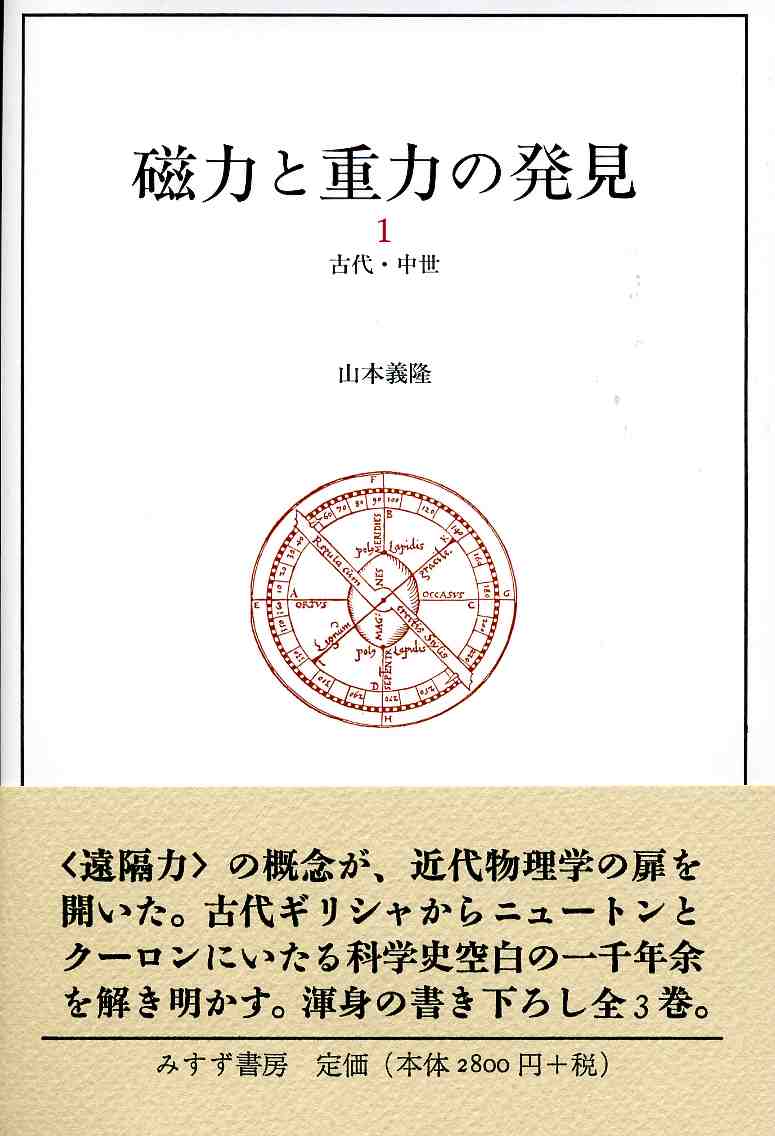
【概略目次】
――第1巻――
序文 1
第1章:磁気学の始まり――古代ギリシャ 17
第2章:ヘレニズムの時代 58
第3章:ローマ帝国の時代 94
第4章:中世キリスト教世界 129
第5章:中世社会の転換と磁石の指向性の発見 165
第6章:トマス・アクィナスの磁力理解 199
第7章:ロジャー・ベーコンと磁力の伝播 232
第8章:ペトロス・ペレグリヌスと『磁気書簡』 268
注 [1-20]
【書評】※Copyright 2003 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
物理学における「力」概念の歴史的発展をたどった本.とくに「遠隔力」をめぐるさまざまな言説を通じて,【魔術】(誤解されやすい言葉だが)が近代科学の成立に果たした役割を再評価する.序文に書かれてあるように,「力」のような「特定の問題の解決や個別的な概念の形成」(p.1)についての科学史的研究がこれまで乏しかったという認識のもとに,グローバルではなくローカルな視点で物理学の歴史を追究する.
とりわけ著者が注目するのは〈中世〉である.ギリシャ時代の再発見を契機としてルネサンス以降の近代科学が生まれ出てくるのだが,その間に挟まれた〈中世〉の果たした役割は無視され,「千年余は完全に空白になって」(p.13)いた.科学と魔術が入り交じっていたこの〈中世〉をもういちど読み直すのが,本書のもっとも意欲的な目標である.
第1巻では,古代ギリシャのプラトンに始まって,ローマ帝国,中世のキリスト教世界を経て,ルネサンス「前」までの「力」概念史をたどる.
第1章は古代ギリシャの自然哲学.遠隔作用をもつ磁力の不思議さは昔から知られていた.とくに,琥珀のもつ静電気作用は数々の博物学書にも伝えられるほど,人々の関心を集めた.古代ギリシャにあっては,磁石はのもつ遠隔力の起源を説明するために,1)「物活論」――遠隔作用は万物には霊的な生命[anima]に由来するというタレスの主張(p.18);2)「還元論」――目に見えない近接作用に還元できるというプラトンの主張(p.54)の対立があった.この対立する見解はその後も永続する.
第2章では,本書全体を貫く,このふたつの対立する自然観について論議が進む――「物活論」vs「還元論」の対立は,言い換えるならば,有機体的全体論に基づく遠隔作用論vs機械論的還元論に基づく近接作用論の対立だと著者は言う(pp.59,91).しかし,中世がはじまるとともに,近接作用論は千年の忘却を体験する>
第3章はローマ帝国時代.磁石の遠隔作用はプリニウスの博物学書(p.117)などを通じて広く知られるようになったものの,その解明はむしろ後退した.それに代わって「自然の共感/反感」(p.118)というような解釈が登場することになる.実験や観察ではなく,文献からの孫引きのもたらした弊害は甚大だった.
第4章は中世キリスト教のもとでの自然研究のありさま.しかし,そのような閉塞状況にあっても中世の「力」に対する関心は方々で発現する.11〜12世紀にかけて再発見されたギリシャ時代の文化的蓄積がイスラム圏を通じて大量にラテン語に翻訳移入されることにより(p.178),キリスト教に対抗する経験的知識の威力が徐々にではあるが認識されるようになる.
関心が湧く点は,この〈中世〉にあって経験的知識あるいは経験主義的立場がどのように維持されてきたのかということ.著者は,第6章で,中世スコラ哲学を代表するトマス・アクィナスに注目する(第6章).彼は異教徒と闘うには,宗教ではなくむしろ哲学(科学的真理:scientia)を武器とすべきだと考えた(p.210).このラインに沿って,トマスは「異教徒」アリストテレスとキリスト教とを融合することで〈スコラ哲学〉を成立させた(p.211).真理と信仰とは矛盾しないというトマスの立場は,キリスト教世界の枠内で「自然学」を可能にしたと著者は考える(p.213).
おそらくこの文脈では,中世の存在論(形而上学)についてもっと掘り下げるべきだったのだろうと思う.しかし,著者は「本質主義」についてちらっと言及するだけで(p.230),それ以上は議論していない.全体を通じて言えるのは,形而上学に関わる論議にはできるだけ触れないようにしつつ,「力」の概念の成立を論じていることだ.第3巻の結末で明らかになることだが,最終的には形而上学を棚上げにしたところに近代物理学が成立したという著者の見解のもとでは,形而上学が脇役にまわされるのはしかたがないことなのだろう.
続く第7章では,13世紀のロジャー・ベーコンの「経験学」(scientia experimentalis)が取り上げられる.現実の自然界に比べたときのスコラ哲学の貧しさを痛感したベーコンは,演繹科学だけではなく帰納科学の重要性を強調する(p.242).磁石の遠隔作用についても,ベーコンは近接作用の立場から合理的な説明を試みた(p.266).ベーコンと同時代のペレグリヌスによる『磁気書簡』は,磁石の極性などの性質を指摘した最初の著作である(第8章).彼はまさに「経験の巨匠」(p.287)だった.
第2章では,本書全体を貫く,このふたつの対立する自然観について論議が進む――「物活論」vs「還元論」の対立は,言い換えるならば,有機体的全体論に基づく遠隔作用論vs機械論的還元論に基づく近接作用論の対立だと著者は言う(pp.59,91).しかし,中世がはじまるとともに,近接作用論は千年の忘却を体験する>
第3章はローマ帝国時代.磁石の遠隔作用はプリニウスの博物学書(p.117)などを通じて広く知られるようになったものの,その解明はむしろ後退した.それに代わって「自然の共感/反感」(p.118)というような解釈が登場することになる.実験や観察ではなく,文献からの孫引きのもたらした弊害は甚大だった.
第4章は中世キリスト教のもとでの自然研究のありさま.しかし,そのような閉塞状況にあっても中世の「力」に対する関心は方々で発現する.11〜12世紀にかけて再発見されたギリシャ時代の文化的蓄積がイスラム圏を通じて大量にラテン語に翻訳移入されることにより(p.178),キリスト教に対抗する経験的知識の威力が徐々にではあるが認識されるようになる.
関心が湧く点は,この〈中世〉にあって経験的知識あるいは経験主義的立場がどのように維持されてきたのかということ.著者は,第6章で,中世スコラ哲学を代表するトマス・アクィナスに注目する(第6章).彼は異教徒と闘うには,宗教ではなくむしろ哲学(科学的真理:scientia)を武器とすべきだと考えた(p.210).このラインに沿って,トマスは「異教徒」アリストテレスとキリスト教とを融合することで〈スコラ哲学〉を成立させた(p.211).真理と信仰とは矛盾しないというトマスの立場は,キリスト教世界の枠内で「自然学」を可能にしたと著者は考える(p.213).
おそらくこの文脈では,中世の存在論(形而上学)についてもっと掘り下げるべきだったのだろうと思う.しかし,著者は「本質主義」についてちらっと言及するだけで(p.230),それ以上は議論していない.全体を通じて言えるのは,形而上学に関わる論議にはできるだけ触れないようにしつつ,「力」の概念の成立を論じていることだ.第3巻の結末で明らかになることだが,最終的には形而上学を棚上げにしたところに近代物理学が成立したという著者の見解のもとでは,形而上学が脇役にまわされるのはしかたがないことなのだろう.
続く第7章では,13世紀のロジャー・ベーコンの「経験学」(scientia experimentalis)が取り上げられる.現実の自然界に比べたときのスコラ哲学の貧しさを痛感したベーコンは,演繹科学だけではなく帰納科学の重要性を強調する(p.242).磁石の遠隔作用についても,ベーコンは近接作用の立場から合理的な説明を試みた(p.266).ベーコンと同時代のペレグリヌスによる『磁気書簡』は,磁石の極性などの性質を指摘した最初の著作である(第8章).彼はまさに「経験の巨匠」(p.287)だった.