【書名】Savage: The life and times of Jemmy Button
【著者】Nick Hazlewood
【発行】2000年03月
【出版】Hodder & Stoughton, London
【頁数】xvi+384pp.
【ISBN】0-340-73911-8
【価格】£12.99 (Hardcover)
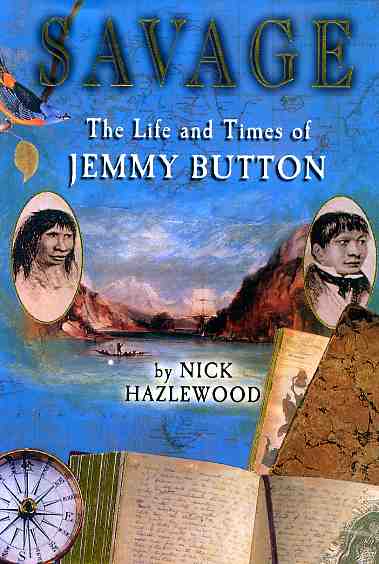
【書評】※Copyright 2001 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
チャールズ・ダーウィンが乗り込んだビーグル号の有名な世界一周航海は1831〜1836年のことですが、本書では同じビーグル号によるその前の南米航海(1826〜1830年)から話が始まります。どちらの航海も船長はロバート・フィッツロイでした。本書は、このビーグル号南米航海のおりに「誘拐」された、パタゴニアのフェゴ島の先住民であるOrundellico(通名Jemmy Button)の生涯をたどります。
フィッツロイ船長の話し相手としてダーウィンが乗り込んだ後のビーグル号航海では、Jemmy Button は他の二人のフェゴ島人とともに過ごしたイギリスでの一年あまりの滞在を終えて、フェゴ島への帰途にありました。前半部分(Part One - Three)では、その航海中ダーウィンとも頻繁に接し、ダーウィンの人間進化観に大きな影響を与えたButtonがそもそもなぜイギリスに送られることになったのかを、それを終始支援し続けたフィッツロイ船長の意図や意気込みとともに描いています。
16世紀にポルトガルのマゼランが発見したパタゴニアのティエラ・デル・フェゴ(「火の島」)付近の海域は、その過酷な環境にもかかわらず大西洋と太平洋とを結ぶ船舶交通上の要衝として重要視されていました。ポルトガル、オランダ、そしてイギリスといった主要国が地の果ての南米南端部に次々に船団を派遣して海路を切り開いたのも、ひとえに商業上の価値があったからのことです。もしも、パタゴニア地域に東南アジアの香料諸島のような意味での経済的付加価値があったならば、きっとジャイルズ・ミルトン著『スパイス戦争:大航海時代の冒険者たち』(2000年12月05日刊行,朝日出版社)に描かれたような世界史的事件に発展したのでしょうが、たまたま生物地理学的な偶然により、フェゴ島あたりにはニクズク的な経済植物はありませんでした。しかし、このような過酷な地域にもフェゴ島人という先住民(indigenous people)が住んでいました。第1部では、ティエラ・デル・フェゴの地理と環境、そこに住む先住民の生活、そして諸外国の進出の経緯について触れています。
ダーウィンによるビーグル号航海記をはじめ、フェゴ島ならびにフェゴ島人に関する記述はこれまでにもたくさんあるが、本書のスタンスは「フェゴ島人の立場」からこの経緯をもう一度考えて見ようという点にあります(p.12)。本書の主人公である Jemmy Button こと Orundellico は15歳のとき(1830年)にフィッツロイ船長率いるビーグル号に拉致され、イギリスに連れ帰られました。
ビーグル号がアドヴェンチャー号とともに南米航海に出発したのは(1826年〜)、より安全な航路の発見という目的があったからです(p.18)。フィッツロイはビーグル号の船長が航海途中で自殺したために、急遽、新船長に任命されました(p.20)。激昂しやすく、しかも鬱("blue evils")にも悩まされたフィッツロイ船長の気質はこの航海の時にすでに発現しています。とりわけ、フェゴ島人との接触が険悪となり、ボートや物資を盗まれるにいたってからは(p.29)、フィッツロイは切れ続けました。
しかし、それと同時に、フィッツロイはフェゴ島人という【野蛮人】に対する別の考えをもっていました。それは、フェゴ島先住民に見られる人間としての「低い地位」を向上させるためには、先住民の再教育が必要なのではないかという考えでした(p.34)。この考えを実践するために、フィッツロイは現地人を「誘拐」し、母国に連れ帰って教育を受けさせた上で、再びフェゴ島に戻すという計画を立てました(pp.41-42)。Jemmy Button を含む4人のフェゴ島人が誘拐されたのは、フィッツロイのもくろみがあったからでした。
1830年、ビーグル号はイギリスに帰還し、Jemmy らは再教育のプログラムを受けることになります。私にとって意外だったのは、フェゴ島人再教育にかけるフィッツロイ船長の意気込みでした。フェゴ島人が伝染病にかかりやすいことを知っていたフィッツロイは、当時ヨーロッパで流行していた天然痘を警戒し(実際、帰国途中に天然痘に感染してしまった一人のフェゴ島人はイギリス到着後まもなく死亡した)、上陸直後にフェゴ島人たちを海軍病院に入院させた上で、その頃普及し始めたばかりの種痘接種を受けさせています。また、再教育のための受入先を苦労して見つけ出したり、私財を投入したりと、イギリスに寄港する前から奔走しました(pp.49ff.)。
ようやくフェゴ島人の受入先がロンドン郊外Walthamstowにあるキリスト教系の学校に決まり、Jemmy たちが通い始めた後も、フィッツロイは後見人として彼らの情報を集め続けます(pp.69ff.)。Jemmy たちの教育内容は英語や宗教だったわけですが、フィッツロイは彼らを周囲の「好奇の目」に晒さないように、半ば隔離するかのように接触する範囲を限定しました(p.86)。つまり、フィッツロイにとって彼らフェゴ島人は決して「科学上の標本」(p.87)ではなく(フィッツロイが入れ込んでいた骨相学的診断はおこなったが)、将来、フェゴ島を文明化する先兵として彼らを待遇していたことがうかがえます。あまつさえ、フェゴ島の言語の語彙集まで手がけたというフィッツロイの姿勢は特筆に値します(意外だなぁ)。
Jemmy らを地質学者 Roderick Mutchison や国王 William 4世に会わせるというのも、フィッツロイの計算が裏にありました。
さて、帰国直後から早くも2度目のビーグル号航海を計画し始めたフィッツロイは、"blue evils"にならないように話し相手として若いチャールズ・ダーウィンを選び(pp.99-100)、同時に Jemmy たちの帰国準備に取り掛かります。ビーグル号の世界一周航海は1831年にイギリスを船出するわけですが、ダーウィンが「そこ」に乗り込んだ理由、そして Jemmy たちフェゴ島人が「そこ」にいた理由は、上に書かれたとおりです。
いずれにせよ、ダーウィンが同船したフェゴ島人に強い関心を示したことは確かです。1833年にビーグル号がティエラ・デル・フェゴに到着した後、Jemmy たちの現地への受け入れでごたごたした経緯をつぶさに観察し、また彼らがどのように元の環境に同化していったか(フィッツロイは「先兵」たちによる「文明化」が進まなかったことにがっくりしたわけだが)を記録したダーウィンは、「ヒトもまた進化できるのだ」(p.151)という見解にたどり着きました。フィッツロイやダーウィンたちはその後太平洋に抜けてしまい、Jemmy たちとは永遠に別れることになります。
では、ティエラ・デル・フェゴに帰った Jemmy たちは、その後どのような運命をたどったのか−これが後半の章のテーマになります。1820年代から30年代にかけてのビーグル号の2度にわたる南米航海を通じて、フェゴ島人の【文明化】ならびに【キリスト教化】が不可能ではないらしいことがイギリス社会に認識されるにいたりました。アレン・ガーディナーはフィッツロイの功績に刺激され、1841年に『パタゴニア伝道協会』という組織を設立し、現地人の再教育を通じての文明化とキリスト教化を組織的に進めようと考えました。ところが、ガーディナーには、宗教的な熱意はあったものの、実際どのように事業を進めればいいのかについてのビジョンがありませんでした。にもかかわらず、1850年に彼は船を仕立てて、フェゴ島に向かい、そこで乗組員ともども全員が死ぬという事件にいたります(p.159)。
ところが、皮肉なことに、この遭難事件は社会的な注目を集める結果となり、それまでまったく財政的援助が得られなかったパタゴニア伝道協会には、人と金が集まることになりました。そして、パタゴニアに近いフォークランド諸島を「再教育」の場として整備し、現地人をそこに連れてくるという案が浮上することになります(pp.160-161)。さらに、創立者ガーディナーを顕彰して、「アレン・ガーディナー号」という伝道船まで建造されることになりました。
こうしてガーディナーの計画は彼の死後によみがえることになったのですが、この事業の目的をどのように設定し、それをどのような手順で実行するかに関しては、やはり充分な議論が尽くされたわけではありません。このことが後で尾を引きます。
1854年にウィリアム・パーカー・スノウを船長としてイギリスを出港したアレン・ガーディナー号は、翌年にフォークランドに到達し、予定通り居住地が建設されました。ところが、どのようにしてフェゴ島人をフォークランドまで連れてくるのかという肝心の点に関して、フォークランド総督のジョージ・レニーとスノウ船長との間で激しい対立が起ってしまいます(p.169)。フィッツロイと同じように「誘拐してでも」連れてくればよいと言うレニーに対し、スノウはそれでは「奴隷の狩り集め」と変わりがないではないかと反発しました。基本路線の対立を抱えたまま、アレン・ガーディナー号はフェゴ島に向かい、スノウ船長は22年ぶりにジェミーとの対面を果たしました。スノウはフォークランドに来ないかとジェミーを誘うのですが、拒否されます(p.177)。
フェゴ島人に拒否されたことにより、協会のフォークランド計画は進捗しなくなりました。イギリス本国の協会から派遣されたジョージ・パケナム・デスパードは、フェゴ島人を集めるためにもっと「積極的」な方法が必要だと述べ、それに反対するスノウとの対立が深まり、結局はスノウは協会から解雇されてしまいました(p.188)。解雇されたスノウはこれ以後、ことあるごとに協会の事業に対して批判を繰り返すにいたります。
フォークランド計画は、スノウに代わって、デスパードが取り仕切ることになりました。1858年にフェゴ島にわたったデスパードは再びジェミーに、家族連れOKなどの条件を提示してフォークランド滞在を要請し、やっとのことで了解を取りつけました(p.195)。しかし、5ヶ月にわたるフォークランドの滞在中に、協会側はジェミーの怠惰さに評価を下げ、むしろ彼の息子のスリーボーイズの能力に関心を向けます。
ジェミー一家の帰国後、翌年にはさらに9人のフェゴ島人がフォークランドで教育を受けることになりました(p.222)。フェゴ島人がフォークランドに来ることにより、協会としての事業は表向きは進捗しているようにみえたものの、教育効果そのものはほとんどなかったことがしだいに判明してきます。帰国の途につく9人を乗せたアレン・ガーディナー号が途中寄港したおり、物資の盗難事件が発生し、その嫌疑がフェゴ島人に向けられました。さらに、フェゴ島に到着したところジェミーが協会からの贈り物に対して不平を言ったことから、両者の関係が急速に悪化し、1859年の11月に船は襲撃を受け、協会に所属する乗組員8名がフェゴ島人に殺されるという事件が起きました(pp.252-253)。唯一の生存者の証言によりジェミーがこの事件の主犯ではないかとの疑いがもたれたのですが、決定的証拠に欠け、最終的に真相は不明なまま、事件は幕を引きました(p.285)。イギリス国内でも、フェゴ島人を責めるべきではないという論調が強かったとか(p.288)。
このような不幸な事件にもかかわらず、協会は当初の予定通り、フォークランドでの再教育事業を続行します。1861年、デスパードの後任としてやってきたウェイト・スターリングは、続く4年間の間に合計50人を越えるフェゴ島人をフォークランドに滞在させました(p.308)。
ジェミーは外来の病原菌のため1864年に死にました(p.309)。フェゴ島人が外国人のもたらす“germs”の犠牲になるという構図はこの後も大規模に続きます。彼の息子スリーボーイズら4人のフェゴ島人は翌年イギリスに渡り、スターリングの強力な後押しのもと、6ヶ月の滞在を成功裡に終えました(p.313)。
1866年に「南アメリカ伝道協会」と改名した協会は、フォークランドではなく、フェゴ島への居住を目的として、1871年にスターリングの部下であるトマス・ブリジェズ一家を送りました(p.319)。ブリジェズはフェゴ島語の大きな辞書を編纂するという仕事に従事しました(p.323)。ブリジェズの辞書に関心を示したのは、ビーグル号航海以来まったく海外に出なかったチャールズ・ダーウィンです。フェゴ島人との接触が、彼にとって多くの情報をもたらしたことは明らかですが(『種の起源』や『人間の進化』での頻繁な言及から見て)、ダーウィンはブリジェズに頻繁に手紙を書き、フェゴ島人の生活習慣と感情表現に関する問い合わせをしています(p.341)。1878年には、協会からの依頼により、ダーウィンはジェミーの孫への援助金をも送っています(p.343)。1882年の死の直前まで、ダーウィンはフェゴ島人に関心をもち続けていたことを本書の著者はダーウィン書簡などを踏まえて明らかにしました。
最終章は苦いです。1884年にフェゴ島に進駐してきたアルゼンチン軍のもたらした病原菌(はしか)により、1ヶ月後のフェゴ島人の人口は一挙に半減し、続く1年の間にさらに半分になってしまいました(p.348)。外来の“germ”の猛威はすさまじかったようです。追い打ちをかけるように、フェゴ島に送り込まれた囚人、金を求めてやってきた者、そして羊の放牧者ら多くの外来者により、フェゴ島人への“genocide”があり、さらにフェゴ人の人口は減少し続け、現在では純粋なフェゴ島人はすでに絶滅しただろうと推測されます(p.354)。
本書のタイトルが示しているように、【野蛮人】とは当時のイギリス社会にとって何を意味していたのかが大きな問題です。フィッツロイにしろ協会関係者にしろ、現地人を「再教育・文明化・キリスト教化」すれば、「みじめな境遇」からの脱出が可能だろうという善意から困難な事業を進めたわけです。ところが、フェゴ島でフィッツロイを落胆させたほど「原始生活に戻ってしまった」ジェミー自身は、そういう同情をいっさい拒否するように、「Life is good; I am hearty, sir, never better」(p.145)と言います。この「落差」を相互に理解しあえなかったという事実が私には印象的でした。
【目次】
List of Illustlations ix
Part One: Land of fire 3
Part Two: Inglan 47
Part Three: Twenty dwarf hairs 107
Part Four: The selfish crotchet 153
Part Five: This studied concealment... 255
Part Six: The Fall 305
Bibliography and Sources 361
Acknowledgements 375
Index 377