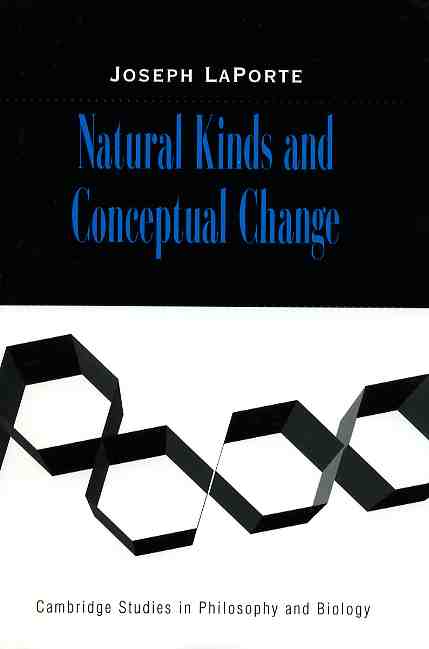 【書名】Natural Kinds and Conceptual Change
【書名】Natural Kinds and Conceptual Change【著者】Joseph LaPorte
【刊行】January 2004
【出版】Cambridge Univerisity Press, Cambridge
【叢書】Cambridge Studies in Philosophy and Biology
【頁数】x+221 pp.
【定価】US$ 70.00 (hardcover)
【ISBN】0-521-82599-7
【感想】
タイトルだけからはとても想像できないがこの本,相当に「分類学哲学」寄りの本であることを知る.かつての【種】問題に加えて,これからは【分類】問題も生物学哲学の観点から再びクローズアップされてくるのだろう.かつては体系学派の抗争が焦点だったが,今回は分類体系の構築にからむ概念的問題群(【種】と高次分類群)ならびに実践的問題群(命名法やランキング)が縦糸となり,一元論/多元論が横糸となる構図か.分類パターン認知というテーマも論議の端々に顔をのぞかせているので,論議の土俵そのものもこれから推移していくかもしれない.リンネ分類体系の認知的特性は Scott Atran (1990) の本『Cognitive Foundations of Natural History』(Cambridge University Press)が典拠として繰り返し登場しているから.
分類学とかナチュラル・ヒストリーは,確かに現代科学としてはマイナーであって(とくに他の“ビッグ・サイエンス”と比較すると),そこで得た結論を〈一般化〉できないのではないかという危惧は科学論の側にはあると思います.しかし,そもそも〈一般化〉された科学論すなわちさまざまな科学に適用し得る言説を論じる価値はもうないのではないかとぼくは考えます.仮説のテスト可能性とか最節約性というかつては〈グローバル〉な科学の話題とみなされていたものが,いまでは〈ローカル〉な個別科学の話題として経験科学的な科学論解析にまわされるようになってきたのはその現われでしょう.
科学論の大きな流れとして〈グローバル〉から〈ローカル〉へという潮流があるのでしょう.科学論(科学哲学や科学史)は科学の「外」に超然と立って見下ろすというスタンスではもうダメで,科学の系譜の「中」に入り込み,個々の科学クレードに寄り添いつつローカルな科学論的論議を展開していくという方向がすでに確定しているという気がします.博物学をケーススタディーとして得た科学論的考察を他の学問分野にそのまま拡張しても当てはまらないかもしれない.しかし,そもそもそういう科学論的な「拡大解釈」とか「使いまわし」はもう不可能だろうというのがぼくの予想です.科学そのものが「系譜(lineage)」の集まりであって,けっして「クラス」ではないということから導かれる帰結です.魅惑的に見える〈壮大な科学論〉にはもう出番は回ってこないでしょう.
Larry Laudan の〈規範的自然主義〉なんかローカル追認そのものに見える.アブナイといえばアブナイ(それが“歯止め”になるのか).でも,科学の「外」から科学論的ブレーキをかけるのではなく,むしろ「中」に科学論的制御棒を最初から仕込んでおくということなら,なかなか賢いことを考えてるなと感心したりする.共生の道を選ぶということかな.ある意味では捨て身の戦法か.Laudan (1984)『Science and Values』(University of California Press)はひもとく価値があるかも.
著者LaPorteが,Kripke / Putnum のラインで分類学を再構築しようというのは少なくともムリがあるように感じる.もちろん,「可能世界」論の観点から〈natural kind〉を復権させようという意図はよくわかる.しかし,「natural kind is a kind with explanatory value. (p.19)」というような「再定義」と随所で出くわす.〈natural kind term〉が日常語由来であるという認識があるのであれば,そして,何よりも〈kind〉という概念が日常会話の中で発生するというのであれば,〈natural kind〉はほかならない認知心理的産物であると言うのが適切だと思うのだが,この本ではそういう「認知科学」との関わりはいっさい触れられていない.
【種】や【分類群】が Kripke 的な意味での〈rigid designator〉であるというのが前半章の主たる論点の一つらしいが,ぼくには説得力のある論議の展開であるとは感じられなかった.対立枠となり得る Ghiselin や Hull の「個物説」へのコメントも,「反駁する必要はない」(p.17)でおしまい.要するに,日常的な意味での「kind」が構築できれば,あとの Kripke 的議論は自由に編み出せるということか.はずしている.
この著者,わかってないね.というか,なんでもかんでも〈Kripke化〉すればすむと思いこんでいるようだ.たとえば,哺乳類(Mammalia)クレードの共通祖先を G とするとき,次のように言う:「Mammalia therefore has some necessary properties. It is necessary such that it includes all organisms in G or descended from G. And it is necessarily such that it includes only organisms in G or descended from G. [p.12]」.要するに「having G for a stem」があるクレードの本質的性質であるという主張である.そして,続く第2章では,このような本質的定義をもつタクソンは,Kripke 的な意味での「rigid designator」(p.36)であると主張される.すなわち〈可能世界〉のすべてにわたって,そのタクソンの同一性がいえるということらしい.
まったく「なに言ってんだか」って感じ−−「Scientists are free to pick an expression, say 'G-clade', and just stipulate that it does refer to that group. If they do so, then 'G-clade' rigidly designates, de jure, that group. So there is no worry that 'G-clade' fails to designate the right group rigidly. [p.47]」.それがどーした? ある研究者が「これはクレードね」と言ったからといって,それが何らかの経験的基盤の上で意味のある発言かどうかは,それが〈kind〉だとか〈rigid designator〉であると指摘したところでプラスにもマイナスにもならない.「可能世界」?――可能な系統樹からなる広大な探索空間を考えれば,あるクレードは別の可能世界では消えてなくなるはずだ.経験科学の中で〈可能世界〉を論じたいのであればそれなりの覚悟が必要だろうと思う.※この本,ダメじゃん.
もしも,この本のメッセージが「心理的本質主義の Kripke 化」であったとしたら,著者の言わんとすることはたいへんよく理解できる.同時に,この本が〈進化〉や〈系統〉とはもちろんのこと,ぼくが関心をもつ〈分類〉とも無縁の本であることがわかってしまう.※早々に引導をわたしてしまってどーするって?(失せる読書慾)
【目次】
Preface ix
Introduction 1
Not in Question: The Causal Theory of Reference
1. What Is a Natural Kind, and Do Biological Taxa Qualify? 8
I.2. Historical Kinds
I.3. Species' Essences
I.4. Ostension
I.5. Laws About Particular Species
I.6. Kinds vs. Individuals
II.2. Naturalness in Respects and Degrees
II.3. High Standards
II.4. Low Standards
II.5. Natural Kind Terms from the Vernacular
II.5.a.ii The Litany of Artificial Kinds
2. Natural Kinds, Rigidity, and Essence 33
I.2. Two Types of Identity Statements for Kinds
I.2.b. A Parallel to 'Hesperus = Phosphorus'
I.4. Rigidity without Power?
I.5. Rigidity and Externalism
I.6. Beyond Names: Theoretical Identity Statements
I.7. Descriptions and De Jure Rigidity
I.8. Theoretical Identities and Changing Meanings
I.9. Nominal Essences or Real Essences?
II.2. On Essentially Belonging to a Species
II.2.b. Essentialism's Status without Cladism
II.2.c. Essences of Species vis-a-vis Essentially Belonging to Species
3. Biological Kind Term Reference and the Discovery of Essence 63
II. Essences and Competing Schools
II.2. Higher Taxa
IV. Vernacular Use
IV.2. Multiple Uses and the Vernacular
4. Chemical Kind Term Reference and the Discovery of Essence 92
I.2. Open Texture Refined
I.3. Jade in the West
I.4. The Moral of Jade
III. Related Microstructures
IV. Looking Ahead
5. Linguistic Change and Incommensurability 112
I.2. Description Theories Lead to Incommensurability
I.3. The Causal Theory's Failed Solution
II.2. Does Language Force Disagreement?
II.3. Scientific Progress
II.3.b. From Vagueness to Precision
II.3.b.ii. Giving Accuracy Its Due
III.2. The "Vitalism" of Past Speakers
III.3. Chance and the Inevitability of Scientific Progress
III.4. Politics and Misrepresentation
IV.2. A Weak Interpretation
IV.3. A Moderate Interpretation
IV.3.b. Kuhnian Local Holism
6. Meaning Change, Theory Change, and Analyticity 150
I.2. Theory Change, Then Meaning Change
I.2.b. The Meaning Change
II.2. A commitment to Synonymy and Analyticity
II.2.b. Why There Is a Commitment to Analyticity
II.2.c. A Commitment to Lasting Synonymy
IV. Conclusions for the Causal Theory of Reference
References 201
Index 215