【書名】Franz Boas: The Early Years, 1858-1906
【著者】Douglas Cole
【刊行】1999年
【出版】Douglas & McIntyre, Vancouver
【頁数】viii+360 pp.
【価格】US$ 35.00 (hardcover)
【ISBN】1-55054-746-1
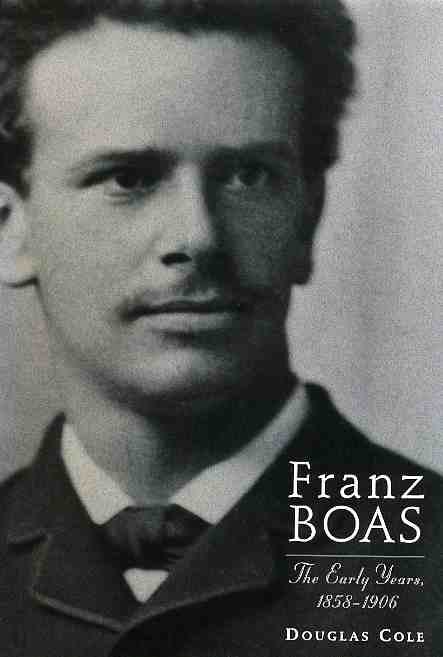
【書評】※Copyright 2001 by MINAKA Nobuhiro. All rights reserved
著者 D. Cole は Franz Boas の前半生をたどった本書の原稿を書き上げる前に急逝したため(1997年),予定されていた Boas の後半生部分の伝記(下巻)は残念ながら不可能になりました.本書は原稿の段階からすでに注目されており,たとえば Margaret Mead のサモアでの hoaxing を描いた Derek Freeman (1999), The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: A Historical Analysis of Her Samoan Research(Westview Press, Boulder)の最初の章でも引用されています.
Franz Boas(1858〜1942)が19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカ文化人類学に与えた影響は絶大だったが(p.3),彼のたどった生涯は意外に詳しく調べられてはいないそうだ.本書の著者 Douglas Cole は,未発表の書簡など1次資料を駆使して,これまで明らかではなかった Boas の経歴と思想を本書で跡づけた.ただし,残念なことに,Cole 自身が1997年に急逝したため,本来は2巻本になるはずの Boas 伝が上巻のみの出版で断ち切られることになったのはたいへん残念なことだ.出版にこぎつけた今回の伝記では,Boas がドイツからアメリカに移住し,紆余曲折を経て,アメリカ自然史博物館の人類学部門に職を得た後,コロンビア大学に変わるまでの前半生(1858〜1906)を論じている.
Boas は,初期から文化相対主義(cultural relativism)を擁護し,生物学とは切り離された文化決定論(cultural determinism)に基づく文化人類学を確立した.本書では,Boas の初期資料を踏まえつつ,彼が進化論の「どの部分」に対して抵抗したのかを明らかにしている.これまで見られた《Boas=反進化論者》という図式はかなりの修正を迫られるだろう.
Boas の "formative younger years"(p.7)は,母国ドイツにある.いわゆるメルヒェン街道沿いにある Minden(Bremen と Hannover の中間あたりに位置する)に生まれた Boas は,当時ドイツ国内で高まりつつあった反ユダヤ主義(anti-Semitism)の中,幼少時から博物コレクターとしての関心を持ち続け(p.20),Heidelberg 大学では数学と物理学を専攻することになる(p.38).体力には自信のあった Boas はいたるところで決闘(デュエル)の場に出ていったそうで,生涯にわたって残る Boas の「スカーフェイス」はこの頃の名残だという.数ある彼の肖像写真はリタッチされているとか(p.61).
Boas は Kiel 大学で物理学の学位を取ることになるのだが,この頃から唯物論的な世界観に疑念をもつようになり(p.56),新カント派哲学を信奉するようになる.それと同時に,一転して地理学の研究を目指し,グリーンランドの Baffin 島での探査旅行(1883〜1884年)のチャンスをつかむ(p.61).1年に及ぶエスキモー(イヌイット)との生活を通じて,Boas は当初の目的の地図製作だけでなく,彼らの民俗・文化・言語の収集にも励み,しだいに「相対主義」の芽を育てていった(p.79).Boas はグリーンランド行を契機として「民俗学者」に変身したということだ.
ドイツでの就職に期待を持てなくなった Boas はアメリカに新天地を求めた(1884年)が,なかなかいい口に恵まれなかった.やっとのことで Science 誌のライターとして職を得ることができ(p.104),翌年の1887年に結婚した.しかし,研究するための新たな突破口として,British Columbia への探査旅行(英国科学振興協会が企画したもの)に参加した(p.110).その後の Boas の生活はまさに「失敗続き」で(p.119),Clark 大学(1889〜1992年)やシカゴ万博企画(1892〜1894年)など一時的な就職はことごとくうまくいかなかった.アメリカ自然史博物館にようやく入れたのは1896年のことだった.
ニューヨークに移った Boas は,人類学と極地探検に関心をもっている Morris Jesup 館長に働きかけて,同博物館の人類学コレクションを着々と集めると同時に,Columbia 大学と二股をかけて,後進の人類学者の育成に乗り出すことになる(Chap.11〜12).しかし,博物館での展示業務が重荷になってきたこと,そして待遇面での不満が溜まり,結局1905年に博物館を退職して,Columbia大学教授に専念することとなった(Chap.12〜13).
目まぐるしい前半生の経歴の方々で,Boas は学問上の「デュエル」を闘わせている.それは,地理学・民俗学・民族学・人類学などを含む歴史科学が,科学としていかなる地位にあるのか,それはいかなる科学的方法論をもつことができるのかに関わる論争だった.生物進化論に対する Boas の姿勢もこの点から見直す必要がある.すなわち,Boas が一貫して表明した「アンチ進化論」は,「進化」それ自体への反対ではなく,当時の「論」への対決姿勢だったということである(pp.255-256).
その著書『進化と人間行動』の中で,長谷川・長谷川(2000)は,基本的な人間観としての「反・生物論」を次のように定義している:
「社会学者,文化人類学者たち(中略)の主張には...,「遺伝」対「文化」,「本能」対「学習」,「からだ」対「心」といった,完全二分法が成り立つという誤った仮定が含まれています.この二分法は,これらが完全に分けられるとは思っていないにせよ,一般人にも強く染みついているものです.日常的に,私たちのからだの作りは生物学的なものであっても,思考や意志や自分が選択した上での行動は,生物学的なものとは関係がないという暗黙の思いが強くあるのではないでしょうか.これは,デカルト以来の心身二元論に根差すものかもしれません.この考えを仮に「反・生物論」と呼んでおきましょう」(同書, pp.17-18).
とりわけ,文化人類学を長年にわたって支配してきた「反・生物論」は,現在にまで影響力を持つひとつの人類観を形成してきた.Franz Boas と彼の思想は明らかに,この「反・生物論」的な人間観のルーツとみなされている.
Boasは,確かに生物学的決定論に対するアンチテーゼとしての文化相対論・文化決定論に向かって当時の文化人類学を導いた.そして,Boas の後継者たち,たとえば Alfred Kroeber や Robert Lowie が人間の生物的要素を完全に排除した「絶対的な文化決定論」(Freeman 1983, 1999)の立場を宣言するのはそのすぐ後だった.
しかし,そもそも Boas が当時の「進化論」のどのような側面に対して敵対したのかをまず見る必要があるだろう.Boas は「進化」そのものを否定したのではない.むしろ,進化ならびに歴史的要因を大きく評価していたことは確かだ(p.126).とすると,当時の生物進化論に対抗する彼のスタンスは,以下のように要約できる:1)演繹的推論ではなく,帰納的一般化を重視する;2)グローバルな理論ではなく,ローカルな知見の蓄積を目指す;3)主観的価値基準ではなく,相対主義的観点を貫く.これらはいずれも theory ではなく methodology に関わることであるので,順に要約しておく.
1)Boas は一貫して科学方法論としての帰納(induction)に信頼を置いていた(p.128).したがって,アプリオリな理論の押しつけに対してはことのほか敏感で,博物館展示方針をめぐる Otis Mason との論争(1877年:pp.127-129)に見られるように,演繹的な包括的推論を一貫して攻撃し続けた.包括的理論の構築ではなく,むしろ科学方法論に関心のあった Boas は,帰納主義に依拠して,進化論的スペキュレーションに対しては懐疑的だった. ここで注意すべき点は,彼は論拠のないスペキュレーションに対して反対したのであり,生物進化そのものに対して反対していたわけではないという点である.当時の進化理論−たとえば,Ernst Haeckel の一元主義的進化論,Herbert Spencer の社会進化論,そして Lewes Henry Morgan の文化進化論など−には,程度の差はあっても,天下りの包括的スペキュレーションの色合いが強かった.それに対して,物理学の教育を受けてきた Boas は帰納的一般化に基づく経験主義こそ妥当な科学方法論であると考えていた.
2)たとえば,後に Boas は「比較法」批判(1896年:p.191)をしたのだが,複数の結果から過去を推論することに対してきわめて慎重だった.過去に関するグローバルな推論ではなく,むしろローカルな個別の結果を十分に検討することで,因果関係を調べるべきだというのが彼の持論だった.もちろん,彼は民族の通文化比較による歴史学的一般化の可能性を積極的に評価していた(p.129).この「比較法」と「歴史学」のドッキングは,現在の進化学における比較法の適用でも頻繁に用いられている.推定された歴史(進化史)に基づく相互比較(比較法)は,直接的な観察や反復された実験がもともとできない歴史学・進化学におけるテスト可能性をもたらす重要な手法となり得る. しかし,その一方で,Boas は,通文化的な類似性(結果)が必ずしも原因の同一性を意味しないと彼は考えるようになる(p.264).この見解は,結果的に歴史仮説のテスト可能性を著しく低下させることになる.通文化的類似性に基づいて歴史的原因の同一性を推論することは,最節約的な推定を行なうことである.しかし,Boas の主張は,通文化的類似性であっても原因の非同一性が可能であると指摘することによって,あえて非最節約的な結論を擁護している.彼の主張を経験的にテストすることは難しい. Boas は,結果の比較によって共通原因を推論するのではなく,多様な結果−すなわち個々の民族の文化−の詳細な記載からそれぞれの原因を求めるべきだとする(pp.264-265).これは,比較歴史学的アプローチからの撤退にほかならない.結果から共通原因への遡行推論とそのテストを自ら閉ざしているからである.何よりも,この主張は,共通原因−すなわち通文化的に共通する human nature の存在−そのものの過小評価につながる.結果として,彼は現在にまで影響を残す文化決定論の種子を蒔くことになった.
3)Boas が念頭に置いていた科学方法論を概観するかぎり,それは生物進化学の基本的な方法論と何ら矛盾するものではない.むしろ,スペキュレーティブな学説が横行していた当時の進化論のレベルを考えると卓越しているとさえ言える.では,なぜその彼が,生物進化とは断絶された「文化人類学」なる学問体系に奔ってしまったのだろうか. それぞれの民族や文化が対等な地位や価値をもつとみなすならば,通時的(歴史的)類似性ではなくむしろ共時的差異性が興味の対象となる.このとき,歴史学的な比較法の重要性は減少することになる.当時の社会進化論的スペキュレーションは,社会や文化の「直線的進化」を仮定しており,まったく相対主義的ではなかった(p.275).Boas の「論」嫌いはここでも十分に発揮された.
Boas がせっかく比較法に基づく歴史的アプローチをもくろみながら,文化進化の共通原因ではなく,個々の文化の特徴にのみ関心を向けてしまった.そして Boas は,相対主義に導かれて,しだいに文化決定論に傾き,当時の進化論のスペキュレーティブな性格ならびに同時代に燃え上がりつつあった優生主義への反発も相まって,最終的に人間の「生物性」を完全に排除した「文化人類学」が20世紀前半に成立することになる.
本書は,多くの未発表資料や書簡に基づいて,Boas の初期の思想形成をたどった貴重な伝記である.とりわけ,当時の進化論に対する彼の態度がどのようにしてかたちづくられていったのかが随所で言及されており,今日の人類学のベースを再検討する上でも役に立つだろうと思われる.
引用文献
Freeman, D. 1983 Margaret Mead and Samoa: The making and unmaking of an anthropological myth. Cambridge: Harvard University Press. 木村洋二(訳)1995 マーガレット・ミードとサモア. みすず書房.
Freeman, D. 1999 The fateful hoaxing of Margaret Mead: A historical analysis of her Samoan research. Boulder: Westview Press.
長谷川寿一・長谷川眞理子 2000. 進化と人間行動. 東京大学出版会.
【目次】
Foreword by Ira Chaikin and Alex Long vii
Introduction 1
A note on nomenclature 6
1. "My old, good hometown":
Minden, Westphalia 7
2. "What claim can someone like me have been upon fame?":
The boyhood years 17
3. "One learns to be content":
The university years 38
4. "I belong to the men of Anarnitung":
Baffin island 63
5. "How depressing it is":
Between Germany and America 83
6. "The whole field lies before me":
Launching an American career 105
7. "An ardent desire to remove obscurity":
Historian and cosmographer 121
8. "The idea is better than the execution":
Clark docent 137
9. "All our ships have gone aground":
Chicago 152
10. "I have looked into hell":
Temporary work 167
11. "The greatest thing undertaken be any museum":
At the American Museum of Natural History 185
12. "A certain work lies before me here":
Organizing anthropology in New York 204
13. "Nothing has worked out - Or only a little":
Dissatisfaction with the American Museum 223
14. "Fundamental differences of opinion":
Leaving the American Museum 242
15. "Laying clear the complex relations of each individual culture":
Race, culture, and method 261
16. "The human mind has been creative everywhere":
The cultural values of Franz Boas 276
17. "Searching for opportunities in other fields":
A leaf is turned 286
Abbreviations 291
Notes 293
Bibliography 333
Index 350